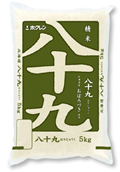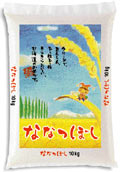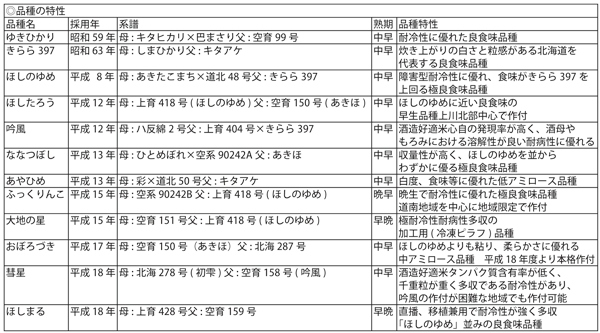食彩 Speciality Foods
〈食彩 2008. 9.18 update〉
コシヒカリに肩を並べた道産米で全道キャンペーン
――根強いコシヒカリ信仰と道産米への偏見・固定観念の打破に向けて
ホクレン農業協同組合連合会
ホクレン(ホクレン農業協同組合連合会)は、収穫を迎える10月に向けて、毎年恒例の道産米キャンペーンを行う。今年度の主力は「ななつぼし」、「ふっくりんこ」、「おぼろづき」で、年々、評価が高まる道産米の販売拡大を目指し、新潟コシヒカリと肩を並べた品質の高さと、衛生的な積雪寒冷地で育った安全性の高さをアピールする方針だ。
■低評価をくつがえした不屈の開拓精神
かつては2等米として評価が低かった道産米だが、冷涼な気候に適した稲を作るため、生産者と農業関係者が一体となって品種改良と栽培技術の確立に向けて取り組んできた。
道立農業試験・研究センターと連携して、世代促進法・葯培養法によって、種苗の育種年限を従来の10年から7年に短縮したほか、食味評価においては理化学的分析値を用いた客観的な評価方法を確立。
また、平成9年からは、全国でも唯一の取り組みとして全道的に高品質米仕分け集荷を展開。特に全国の農産物検査規格では、整粒歩合が70パーセント以上が1等米の基準だが、道産米はそれを上回るよう努力し、さらに精米白度を向上させるなどタンパク含有量の低下に努めてきた。
しかも、寒冷気候で、病害虫や稲熱病などの発生が少ないため農薬使用の必要性も低く、農薬消費額の金額ベースにおいては、本州の87パーセント程度に抑えた低農薬生産が行われている。また、土地改良事業と土づくりによって、化学肥料の使用量も86.5パーセントと、低く抑えられている。
そうした地域的特色を生かしつつ、技術改良の努力を積み重ねた結果、昭和59年に北海道独自のブランド米「ゆきひかり」を開発して後、昭和63年には「きらら397」、平成8年は「ほしのゆめ」、12年は「ほしたろう」、「吟風」、13年は「ななつぼし」、「あやひめ」、15年は「ふっくりんこ」、「大地の星」、17年は「おぼろづき」、18年には「彗星」、「ほしまる」と、ほぼ毎年のように高品質の新ブランドを開発し製品化してきた。
その結果、63年の「きらら397」、平成8年の「ほしのゆめ」、13年の「ななつぼし」は、(財)日本穀物検定協会による食味ランキングにおいて、新潟県魚沼産のコシヒカリの特Aに次ぐAランクに評価された。これは上越コシヒカリ、宮城県ひとめぼれに並ぶもので、A'となった山形県コシヒカリ、秋田県アキタコマチに優る評価である。
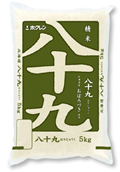 |
 |
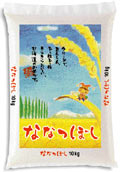 |
| ▲おぼろづき(八十九) |
▲ふっくりんこ |
▲ななつぼし |
■定着した「ななつぼし」に引き続き「おぼろづき」「ふっくりんこ」の販売拡大を柱に展開
全道キャンペーンの主役となる13年の「ななつぼし」は、20年の歳月をかけて開発された。ひとめぼれ×空系90242Aと空育150号(あきほ)の配合によるもので、収量性が高く、ほしのゆめを上回る品種。食味を左右する粘りの元となるアミノペクチン(デンプン)の含有量を、コシヒカリの18.4パーセントに極力近づけて完成された。特色は、つやと粘りと甘みのバランスが優れており、寿司などに最適だ。
15年の「ふっくりんこ」は、道立道南農業試験場で開発された品種で、空系90242Bと上育418号(ほしのゆめ)を配合してできた。晩生で耐冷性に優れており、主に道南地域に限定的に作付けされてきたが、19年産からは作付け地域を拡大する予定だ。ふっくらとして柔らかく、優れた食味が長持ちする特徴があり、「プロ御用達のお米」として、特に和食利用に力を入れている。昨年7月には、品質維持と安定供給のために生産者組織の連携を図り、「ふっくりんこ産地サミット」が開催された。その結果、整粒歩合は80パーセント、玄米白度は19.5以上、精米タンパクは6.9パーセント以下を基本とし、異常気象などで品質維持やロットの確保が困難となった場合は、改めて協議することが決定された。
「おぼろづき」は17年に開発されたが、ホクレンでは18年産よりさらに品質を向上させた「八十九」(はちじゅうく)が売り出された。初年は60トンしか獲れず、しかも米の最高峰である魚沼産コシヒカリに匹敵するその食味から、試験栽培米の販売では「幻のお米」と絶賛された。空育150号(あきほ)と北海287号を交配したもので、うるち米のアミロースの平均含有率20パーセントに対し、14パーセントに抑えているため、ほしのゆめよりも粘りがあり、柔らかさに優れ、冷めても食味が全く劣化しない高品質の中アミロース品種である。山形コシヒカリを越えたおぼろづきを、さらに厳選した高級米として製品化された。
「八十九」のブランド名は、八十八の手間より、さらに一つ多くの手間をかけた意味合いで、アートディレクター・佐藤卓氏によるパッケージデザインでは「八十九」の脇に「おぼろづき使用」と記される形となった。18年度から本格的に作付けし増産体制に入っているが、当初から好評だったために大手ビールメーカーや銀行のキャンペーン景品、高級旅館などで採用され、19年1月には早々と完売してしまった。
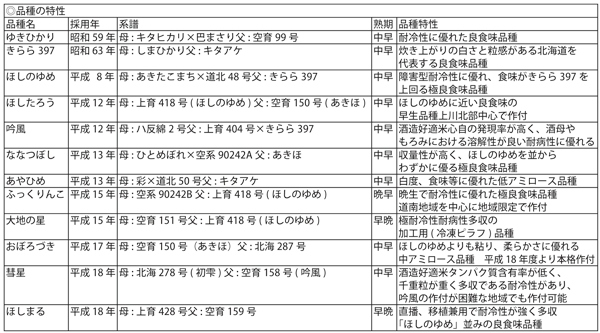 |
■消費者の求める理想の米を実現
2007年にホクレンが行った「お米の消費動向調査」は、北海道、首都圏(1都3県)、東海(愛知)、京阪神(京都、大阪、兵庫)から各500人ずつ、20歳から69歳までの2,000人を対象に行われた。その結果、「最もよく食べているお米」について、今後の意向に関する質問では「ずっと食べ続けたい」とする回答が、京阪神の36パーセントから北海道39パーセントだったのに対し、「もっとおいしいお米があれば変えてみたい」との回答は、東海の43パーセントを最低に、最高は首都・京阪神の47パーセントで、どの地域でも最も多くの割合を占めた。現在、馴染んでいる米にこだわり続ける考えはなく、良いものがあれば積極的に採り入れようという消費者意識が伺える。
さらに「食べてみたいお米」に関する質問では、「減農薬で安全」を選択した回答率が、各地ともトップで、最低は首都圏・京阪神の88パーセントから最高は東海の92パーセントで、9割近くの人々が安全性を重視していることが伺えた。次いで、「冷めてもおいしいお米」、「いつでもおいしいお米」、「熱心な農家」、「自然の多い環境」、「品質管理」と続いており、安全性と食味や品質、そしてそれを裏付ける生産者や生産環境にまで目を向ける消費者心理が伺われる。
そして「食べてみたいお米」の「風味」について、25項目の中から5項目の選択を求めると、「ふっくら」が49〜58パーセントとダントツで、次は「甘みのある」45〜49パーセント、「ツヤツヤ」が33〜40パーセント、「粒がしっかり」は30〜34パーセント、「コシのある」は24〜30パーセント、「もちもち」は23〜35パーセント、「香りのよい」は25〜29パーセントという結果となった。つまり消費者が理想とする米とは、ふっくらとして甘みがあり、精白度が高く、粒が揃っており、香りが良く粘りのある品種ということになり、まさに道産米の改良ポイントに合致していることが判明した。
課題は、道産米に対する旧来の偏見と固定観念をいかにして覆し、ブランドイメージを定着、普及させていくかにある。コシヒカリと同等の食味を持つ道産米を比較する目隠し実験では、コシヒカリに遜色のない対等の評価を得ながらも、ブランドが明示されると結局はコシヒカリを選択してしまう消費者の心理的な壁を、どう解消するかが今後のカギとなる。そのためには、安全性と食味と安定供給を求める消費者の要請に、道産米が完璧にマッチしていることを全国的にアピールし続け、着実に浸透を図っていくことが重要だ。
 |
| ホクレン農業協同組合連合会 |
| 米穀事業本部 米穀部 主食課 |
| 札幌市中央区北4条西1丁目 |
| TEL 011-232-6233 |
|
ホクレングリーンネットショップホームページはこちら
北海道米安心ネットホームページはこちら
HOME