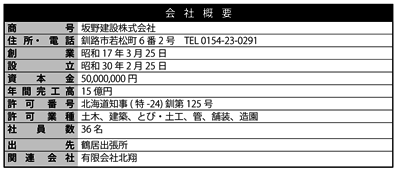|
建設グラフインターネットダイジェスト
〈建設グラフ2012年9月号〉
高規格幹線道路のミッシングリンク解消を訴え要望活動を展開
── 釧路の豊かな自然環境の情報発信に取り組む
釧路建設業協会 根釧開発委員長、坂野建設株式会社 代表取締役社長
坂野 賀孝 氏
- ──昭和17年に設立され、70年が経過しましたね。その70年の間に、創業者をはじめ、代々にわたって釧路建設業協会長などの要職に就任し、坂野社長も釧路建設業協会の根釧開発委員会の委員長という要職に就任していますね
-
坂野 父・坂野勤や祖父・坂野重吉は業界の方々に引き立てられたので、協会の要職が務められたと思います。逆に私は現在の上田光夫会長、各副会長を立てていく立場なのでその繰り返しだと思います。
- ──初代、先代の方々はどんな人柄でしたか
-
坂野 祖父は気が優しく、人間関係を大切にする人でした。父は生真面目で、ひたすら建設業一筋というタイプでした。
- ――建設業が盛んだったのは、先代の時代くらいですか
-
坂野 そうです。昭和40年代後半の頃で、私は中学生・高校生でしたが、会社の従業員が着実に増えていった様子から、会社の業績が伸びていることを感じました。当時は1階が事務所で2階が住居だったので、朝夕の戸締まりをしましたが、いつしか事務所が増築して広くなっていた様子を見てきたので、職住一体の日常生活の中で会社の伸びていく様子を子供なりに感じました。
- ──その会社に入社したのが58年で、平成6年には先代が釧路建設業協会長に就任しましたね
-
坂野 就任した時には立場上、大変だろうと思いました。協会長となれば公務のために、会社を空けることが多くなるので、社内は私が担っていかなければなりません。社外からは協会長の息子として見られますから、業界内でも「協会長の息子だから」などと言われるのも嫌なので、私自身はやりにくい思いはありました。
社内ではNo.2として黒子に徹して仕事をしていました。伝票、現場、営業、内部管理、人事、協会長とのスケジュール調整など会社業務の全てに携わっていたので、体力的にも精神的にもかなりきつい思いをしました。現在の社長業務よりむしろきつかったです。
先代の社長も多忙となり、意思疎通がお互いなかなか取れなくなったので、会長就任期間の6年間は複雑な心境で業務に当たっていました。
また、公職の立場としては、政治とも関わることもあります。当時は鈴木(宗男)先生が釧路に国替えされた時期だったので、そうした政治的な動向を尊重しなければならず、北村先生、鰐淵先生ともどもかなり気を使われていたと記憶しています。
- ──釧路建設業協会も来年で100周年ですが、根釧開発委員会を新設し、社長はその初代委員長に選任されましたね
-
坂野 釧根地域は、全道的な傾向ですが、今年度の開発予算でも新規の道路事業はゼロで、新直轄の本別釧路間の高規格道路が、残る3年間で阿寒町にまで到達する予定です。これで地域の大型プロジェクトは終了するので、このままでは平成29年には国の釧路道路事務所も、最悪の場合は閉鎖になるとの懸念も聞かれます。
また釧路農業事務所も、今年で鶴居地区の農地防災事業が終了するので、 その存廃も気にかかります。両事務所とも道内では知名度ある事務所であり、廃止される事態になれば、私たちの業界も先細りになってしまいます。そこで、地域住民の理解を得ながら次代につながる事業計画を創出することが必要で、それを担ってほしいと依頼されたのが切っ掛けです。
- ──高規格道路は、根室まで計画されないまま途切れているのですか
-
坂野 釧路根室間は線は引かれておりますが、実際は棚上げ状態だと思います。釧路網走間に至っては、さらに計画は遠のいています。
- ──道は6月28日に太平洋岸の津波予想を発表しましたが、そのための対策事業が必要では
-
坂野 「釧路根室圏まちとくらしネットワークフォーラム」という団体が、昨秋に市民防災フォーラムを主催しました。この4月には京都大の藤井聡教授をゲストに招き、2回目を開催しました。その中で聞かれたことですが、釧路市は釧路新道と外環状道路が建設中ですが、当地は太平洋に平行した細長い地形であり、しかも幹線道路も太平洋と平行しており、内陸部に向かう垂直方向の道路網が脆弱なのです。
そのため、非常時には都市機能がストップしてしまうので、釧路新道と外環状道路に交差する震災対応の道路整備がフォーラムで問題提起されました。
- ──昨年の東日本大震災にともなう津波は、釧路市内にも到達しました。避難路の確保は緊急課題ですね
-
坂野 外環状道路は、これまでは高速移動が主目的でしたが、避難機能も持たせる必要があります。民間からそれを求める声を上げていきたいと思います。
外環状道路に乗れれば、そこから鶴居方面に逃げることもできれば、阿寒方面に向かうこともできます。そうした避難路が増えれば、市民の安全度が高まります。
- ──この6月には、民間人の立場で政府陳情にも当たりましたね
-
坂野 釧路根室圏まちとくらしネットワークフォーラムは平成15年に結成され、これまでに5回ほど中央要望していますが、霞ヶ関からは地域が個別に要望にきても迫力はないので、北海道が一体となってはどうかとの提案がありました。
そこで「道ネット」(北海道地域と道をつなぐネットワーク、会長:田中夕貴)が平成18年に結成され、6回程中央要望に行って参りました。地域エゴのための陳情ではなく、オール北海道として地域をどうするかを考えた陳情内容となりました。
そしてこの6月の陳情も道内8人の役員で赴きましたが、今回の主な目的は北見足寄間の凍結路線と、士別名寄間の凍結路線を解除してもらうことでした。
北海道はこうした高規格道路がネットワークとしてつながっていません。この陳情は、釧路市という地域から見れば、直接のメリットはないのですが、全道的な課題として見ればこの2路線が凍結解除されなければ、それに続く釧路根室間の案件など未処理案件が解決できないのです。
また、この陳情に当たっては、民主党の小川勝也代議士が窓口となり、国交省の津島恭一政務官の元まで動行して頂きました。その結果、先日、津島政務官が公務で根室港へ視察された折りに「時間があれば凍結路線を視察したい」と発言されたそうです。私たちの陳情が耳に届いたものと感じ、心強かったですね。
- ──巨大津波が予測されたのですから、国土の強靱化に向けての根本的な見直しが必要ですね
-
坂野 この10年間の公共投資にシーリングをかけるようなやり方から見て、政府は日本の基礎体力たるインフラへの対応が弱々しく、公共事業を軽んずる傾向にあると言わざるを得ません。
道東地域は釧路湿原国立公園、阿寒国立公園そして知床国立公園などの自然資源を擁する東北海道観光の玄関口であり、公共インフラは一定水準以上に維持していかなければならないのに、逆に公共投資予算は半分以下に削減されたのではメンテナンスも困難です。実際に東日本大震災では、釧路市は幣舞橋、久寿里橋、旭橋の三橋が通行止めとなったのですから。
- ──つまり釧路市の中心街の住民は、釧路川をはさんだ丘陵地帯への避難路を絶たれたということですね
-
坂野 交通は完全に麻痺状態となり、それが一日半に及びました。やむなく市民は根室側の釧路町へ迂回し、2〜3時間も時間をかけて移動したのです。市内には釧路川と新釧路川が通り、地区は橋南地区、橋北地区、鉄北(鉄道北)地区と三つに分断されているのです。そこで橋が寸断されると、各ブロックが孤立し機能が麻痺してしまうのです。
釧路市は宮城県仙台平野と同様に太平洋岸に面し、平地に市街地を形成してきた街です。十勝や札幌のように碁盤の目に整備されていれば、移動も迅速にできますが、釧路は非常時の選択肢が狭い道路状況なのです。
一旦非常事態になると一瞬にして交通体系が麻痺してしまうのが釧路市街地の弱点です。
- ──それでも釧路の振興を担う経済人として、釧路の成長要素を見出していかなければなりませんね
-
坂野 水産業は厳しい状況ですが、釧路市は水産のまちであると同時に酪農王国でもあります。観光においても観光立国として、また、日本を代表する一次産業の府県、そして北方領土隣接地区でもあるので優位性は高く、全体的に落ち着きのある街です。
私が入社した当時から比べると、インフラも街並みも格段に変わってきています。人口減少で寂しくはありますが、観光インフラ面では恵まれ、釧路川の整備も精力的に進められています。
中央一極集中を是正し、地方にお金を回さないことには経済パフォーマンスが向上しません。
- ──社長の名刺にデザインされているものの意味は
-
坂野 道内での牛乳の消費量が落ちたので、道民の消費を呼びかけ、生産を上げようという農業団体の活動を耳にし、また道産米についても高橋はるみ北海道知事がCMに出演するなど、道産品の消費奨励に力を入れていました。せっかく地元に高品質のものがあるのだから、それを優先しようと社員にも話し、その気運を高めるために、6年前に名刺のデザインにもそれを取り入れたのです。
- ── 一方、釧路湿原に関連して、湿原塾などさまざまな活動に当たっていますね
-
坂野 昨年から東北海道うま会議の会長を引き受けました。ホーストレッキングを通じた愛好、地域振興を目的としています。
鶴居村のどさんこ牧場を拠点に実施しているホーストレッキングは、本州の利用客のリピーターが多いのです。本州は夏は高温で、乗馬にしても料金は高いのですが、こちらは8,000円程度の格安料金で提供しています。とりわけ東京は人工的なフラットなコースしかありませんが、鶴居は大自然の山間部で伸び伸びと走れます。どさんこ牧場のインストラクターは素晴らしい人達です。釧路町達古武も鶴居村も素晴らしい景勝地です。丹頂鶴とどさんこが風景と一体となっています。
また、釧路湿原塾は東大の月尾嘉男名誉教授が塾長となり、来訪の際には会員と趣味のカヌーで一日を楽しみ、その分、講演料は無償で講演していただくという活動状況です。
こうしたトレッキングやカヌーは、釧路らしい楽しみ方であり魅力と言えます。それを圏外の人々にもPRして知ってもらうことも、観光振興にとって大切な活動だと思います。特に月尾先生は、蛇行する釧路川や釧路湿原などの自然は本州では見られない。これからは発展がキーワードではなく、いかに環境を守るかが大切であり、小さな地方から国を変えようと、よく発言されています。
- ──そうした多様な活動に取り組みつつ、本業は70年を超えましたが、従業員・スタッフにはどんな訓辞をしていますか
-
坂野 本社の人員は現在は36名で、最盛期よりも10人減りました。現下の公共事業縮減の厳しい情勢下で厳しい環境にはあっても、地域に暮らし、地域で糧を得て生活しているので、やはり地元志向を念頭に置いて仕事に臨んで欲しいと話しています。
先日、70周年事業として従業員家族と大阪方面へ旅行へ行って来ました。日頃、従業員の家族とはなかなか対面する機会もないので、社内行事を通じてそうした機会があると、経営者としてのモチベーションも高まります。
- ──北海道の公共投資額について
-
坂野 先般、国の関係者と面会しましたが、その際に話題となったのは民主党への政権交代で農業基盤整備予算が全国的に半減しましたが、釧根管内は前年比で85%もの削減率でした。このために全道のインフラ整備の全体計画のバランスが崩れて個々の予算にミスマッチ起こっているとのことです。公共事業は本来、道路、河川、農業、港湾など全分野のバランスを考えながら事業執行してきているのに、例えば道路のインフラばかり進展しても農業生産力が落ちてしまうことになって事業効果が上がらないのです。
また、農業予算の減少により、港湾の荷役やトラックの輸送も需要が減少します。
事業予算というものは、全体のバランスが大切で、どこか一画の予算が崩れても産業とインフラの相乗効果が減殺されてしまい、地域のGDPは延びていきません。特に釧根地域は酪農王国でもありますから、酪農家が安定した農業収入を上げられないようでは、地域のGDPは延びていきません。
- ──災害時の情報伝達について
-
坂野 地元のFMローカル局がありますが、非常時には大きな役割を果たしています。東日本大震災では、テレビ局は東北全体のことを終日報道しましたが、これでは地元住民は地元の状況が把握できません。しかし、地元のFM関係者が直ちに情報収集のために市役所へ赴いたお陰で、避難所の案内や橋の通行止めなどの情報がどこよりも早く放送されました。今後もこうしたローカルFM局を震災対応の情報拠点として、地域住民と盛り上げていくことが大事だと思いました。
 |
| 坂野 賀孝 さかの・よしたか |
| 昭和34年12月16日 生まれ |
| 昭和57年 3月 専修大学 卒業 |
| 昭和57年 3月 株式会社サミットストア 入社 |
| 昭和58年 6月 坂野建設株式会社 入社 |
| 平成 6年 4月 同社 専務取締役 就任 |
| 平成13年 4月 同社 代表取締役社長 就任 |
|
|