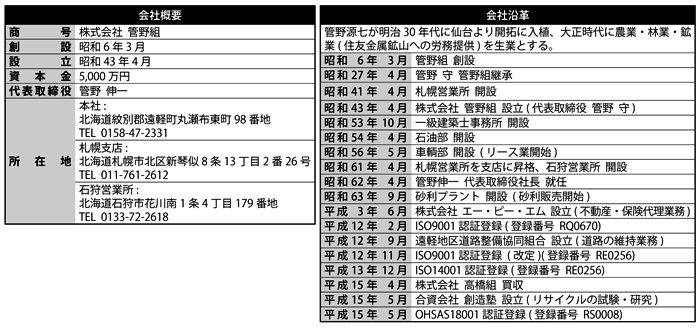|
interview 明治30年仙台からオホーツクに入植
|
 |
- ――昭和6年に創業した初代管野源七氏についてお聞きします
-
管野 私の祖父は仙台出身で、伊達藩の商家の生まれだったとのことです。明治30年代に親族を引き連れて北海道遠軽の地に入植したようです。当時は原生林の中でしょうから、木材を伐採、伐根して開墾し農業に従事しました。伐採した木材は湧別川を利用して湧別港まで輸送していたようです。その一方で、農業に従事していたので、その後、丸瀬布農協の初代の組合長にも就任しました。
大正5年には紋別と丸瀬布間にある鴻之舞で金鉱が発見され、大正6年に住友金属鉱山が買取り、本格的な開発が始まり、東洋一の富鉱金山として栄えました。祖父はこの地域に寮を作り、東北から200人程の坑内員も調達していたようです。そうして管野組が出来上がったようですね。このように農林業の他に人材の調達など、様々な事業を手がけていたので、商才はあったのでしょう。伊達藩は廃藩となったので、当地では商売にならないので、それを畳んで入植してきたということでしょう。
そうして昭和6年には、住友金属鉱山から土木・建築のための人員確保も依頼され、東北から大工などの技術者を調達したのが建設業の始まりでした。丸瀬布側の金山と、その反対側の鴻之舞金山と、この二つによって現在の建設会社である管野組の基礎が出来たのです。しかし、鴻之舞金山は昭和41年まで存続しましたが、丸瀬布側の金山は昭和38で廃業しました。
- ――社長の経歴についてお聞きします
-
管野 私は昭和24年1月の生まれで、父(管野守)が祖父から建設業の管野組を引き継いだのは昭和27年でした。
小学校から高校までは遠軽で、大学は日大商学部を出ました。中学1年生の3学期に生徒会の役員を務めましたが、生徒会顧問の教諭から将来の希望を聞かれたときに、ロカビリーの歌手になりたいと回答したところ「祖父が築き、父が守ってきた管野組という会社を、君が守らないでどうする」と叱られました。「働いている従業員もたくさんいるのだから、責任ある行動をしなさい」と言われ、納得したものです。
しかし、高校に進学してから思ったのですが、その当時の管野組は叔父や親戚らが勤務し、部長職を占めているような職場は、いくら社長の息子でも上に立つのは無理だと感じました。そのため最も有効なのは、資金の流れを抑えることだろうと考えたのです。それには会計を学ぶのが最適と思い、商学部を選択したわけです。
- ――企業グループをトータルに俯瞰できる視点を持つ番頭を目指したことは、正しい判断だったのでは
-
管野 昭和46年に大学を卒業し、日本橋の会計事務所に就職し、そこでいろいろな顧問先を含めて税法や財務諸表など、会計実務を学びました。
私たちの時代は、今とは違って全てを自筆で書いて、計算は算盤を使っていた時代でしたが、昭和50年代からはすべてが電算化され、私もよく資料を持って野村證券のコンピュータールームに通ったものです。そうした経緯から、いち早く電子的な会計業務を経験しました。
- ――Uターンした時に、そうしたシステムを導入したのですか
-
管野 昭和52年6月に管野組に就職しましたが、当時はすべて手書きの伝票会計でした。
翌年には給与計算はPCで行うようになりました。たぶん、この管内で給与計算や日雇い作業員の保険業務を電算化した事例としては、当社が最も早かったでしょう。
昭和56年に、父は私を専務に就任させて営業に出してくれました。お陰で、様々な人脈が構築できました。
- ――さらに、リース業や石油部門など、社業を多角化していきましたね
-
管野 私がUターンした翌年の昭和53年に社屋建設の構想があり、ガソリンスタンドを経営していた㈱谷口油機から提供された敷地に社屋を建設しました。
社屋建設の計画に合わせて、スタンドも買い取って欲しいとの要望で、今日で言うM&Aの手法で昭和53年にそのスタンドを買収し、従業員の研修も同時進行で始め、社内には石油部というセクションを新設しました。
もう一つのリース業務を担う車両部については、他社に重機の借用を依頼するに当たって、社内各部の幹部が単独でまちまちに注文していたので、それらを一元化した方が効率的と考え、昭和56年に組織として新設したのです。
とかくどんぶり勘定の要素が多い業界でしたが、システム化すれば、各部門の業務や原価がお互いに明確に分かるようになりますから、そうした意味も含めて分けたのです。
 |
| ▲建築事業実績:丸瀬布中学校 |
- ――そうして昭和62年に社長に就任しましたが、印象深かったことは
-
管野 駆け出しの頃から函館以外は直接に自分で営業してきましたが、大勢の諸官庁の方々には、ずいぶん可愛がって頂きました。全道の土木現業所(建設管理部)を巡りましたが、所長室に行けば「まぁ、座って茶でも飲め」と厚遇して頂き、そこで一息ついて、また稚内から十勝まで遠出するといった毎日でしたが、楽しかったですね。今とは違って、当時は行政職員の皆様と意思疎通が可能だったので、本当によく処遇してもらいました。
若い職員も幹部職も含め私たち受注者と発注者は、常に地域の安全・安心を一緒になって作り上げていくという意識で、役割分担を分けるのではなく一体となって作っていたような気がします。
- ――昨年は創業80年を迎えましたが、それほど長く安定的に地域の公共事業に携わって来られた秘訣は
- 管野 私も、私の父もそうでしたが、社員とその家族、そして世間の人々を大切にしてきました。「管野組は単独で生きているわけではない」と、社員達には常に言っています。「世間の皆様に認められて、生かして頂いてる」ということを、常々話しています。そこで、ビジネスにおいては地元で手配して活動できるものについては、必ず地場調達しています。地元の商店にも利益が受けられるようにして初めて、三方良しということになります。売り手と買い手だけではなく、その取引が社会全体をも利する精神です。
- ――公共事業が半減する情勢のため、新分野への進出にも着手しましたが、軌道に乗りましたか
-
管野 私が会計実務を専門としてきたことから、ドンブリ勘定はなくなり、各部ごとの原価計算も現場の原価計算もシビアにしました。そのお陰で、ある時期からは無借金経営となったので、社員達にもその自覚は根付いたものと思います。
そして新分野であるじゅんさい事業に進出したのも、公共事業が減るだろうという想定の下に、経営の多角化として着手しました。ただし、通常は銀行融資など他人資本を調達しますが、当社はすべて自己資金で賄っています。
じゅんさいには昭和60年くらいから試行錯誤で着手し、62年から事業化しました。切っ掛けは、車両部の砂利部門が農地を掘削し、原石を採集し、それを洗浄して砂利として販売していましたが、その掘削後には穴が出来るので、そこに水が溜まれば排水し、山土を入れて畑として埋め戻しますます。これにはそれなりの費用がかかるので、どうせ埋め戻すならば、それで設備投資をしようと考えたのです。
 |
| ▲土木事業実績:旭川紋別自動車道 遠軽町 丸瀬布改良工事 |
- ──健康食品を手がけようという発想は、以前からあったのですか
-
管野 その頃に私の東京在住の親戚が、出版した一冊の本を送ってくれました。内容は、老化の原因はムコ多糖の不足にあることを解明したものです。ネバネバした物質の不足が老化の原因になるということで、植物の場合はじゅんさいやおくら、納豆であり、動物の場合は骨髄やうなぎの粘りなどがムコ多糖体というものです。
そこで、このじゅんさいを手がけてみようと考え、何名かの社員を連れて秋田に勉強に行ったり、道内の事業者を視察したのが始まりです。
- ──市場に出荷できるようになるまでに、どのくらいかかりましたか
-
管野 3年くらいだったと思います。地域イベントを利用して出荷しました。北緯44度で、最北端のじゅんさいで、大雪山系の雪解けによる地下水を汲み上げて育成しています。
七飯産の場合は池が深いので、なかなか水温が上がらないのですが、当社の場合は手作りで、池の深さは1m程度に止めてありますから水温が上がりやすい。その分、じゅんさいの粘着物質は豊富になります。もしもこれが海辺に近かったら、塩風に弱いものですから色が悪くなってしまいます。大切なのは鉄分と塩分が無いことが重要な条件ですから。
- ──それによって、高級品となりましたね
- 管野 もっとも当社としては、庶民的な商品として出していこうと考えているので、地元ホテルや地元のイベントなどを通じて出品しています。札幌でもホテルや寿司屋などから引き合いがあれば、選り好みせずに出品します。
- ──量産していく考えはありますか
- 管野 池をもっと拡大して量産はしたいのですが、摘み手の技術がけっこう難しく重労働なのです。そのため、人員を募集してもなかなか応募がないのです。これは本場秋田でも同じ状況で、人手が不足しています。
- ──また、季節限定であるのがネックですね
- 管野 採り手がもっとたくさんいれば、池の面積を拡張して量産も可能ですが、現在は秋田でも伸び悩んでいるとのことです。それで今年の二月に秋田県三種町から、私にじゅんさいについての講演依頼がありました。本当は秋田が本場なのですが、遠軽の私に講演依頼です。
 |
| ▲船を使ってじゅんさいを摘み取る様子 |
- ──現代は高齢化社会ですが、女性が若さを維持していくためにも需要は高いでしょう
- 管野 お陰様で無融資で運営しているので、赤字にはしない代わりに莫大な収益もありません。今のところは収支はゼロのトントンというところです。これが量産できれば、僅かながらも利益は出ると思います。
- ── 一方、本業では網走建設業協会の会長でもありますが、建設業界の使命感についてもお聞きしたい
-
管野 建設業協会の会員は、ピーク時には78社もありましたが、いま現在は58社ですから20社が消滅しています。また賛助会員も200社近くはいたものと思いますが、いまでは100社くらいです。しかし、残ったところはみな健全経営できています。
その全社がこの需給状況で生きられるかどうかは保証できませんが、こうした会員がいるから、このオホーツク総合振興局管内は地域の安全・安心と雇用が確保され、地域経済の活性化を保つことができているとの自負があります。
管内には老朽化したインフラもありますから、国に対してもいろいろと働きかけはしています。
- ──地域を護る地場企業というのは必要ですね
- 管野 お互いの地域を護る企業を尊重し合うからこそ、存続できるのだと思います。各地域の企業が、その地域住民からどのように思われているかを、互いに理解し合っているのです。したがって、その地域にはその企業が必要なのだと、お互いが理解しているので、側面からの協力体制は出来ているつもりです。そして、今後もそういう協会でありたいものだと思っています。したがって、そのために必要な情報はいくらでも提供したいと思っており、私もいくらでも奔走して建設需要も、より多く発掘できるように努力したいと思っています。
- ──地方建設企業のあり方についてお聞きします
-
管野 新分野進出には、国も道も力を入れていますが、これは自己資本をしっかりと持っているところが着手すべきで、他人資本に依存して着手するなら、それが手枷や足枷となります。
M&Aについても同じで、自己資本の中で進めるべきだと思います。融資を受けてまでして手を出すと、大失敗の原因になると思います。
しかし、無為無策でいたのでは、事業は大きくならず、雇用の確保も企業の継続も難しい環境なので、チャンスがあれば不得手な分野や不足部分はM&Aで補足するのが良いと思います。
そして、こうした過疎地域の安心・安全を担保しているのは、間違いなく建設業界ですから、三方良しの考え方を地域に根付かせるためには、地域の人々の目に見えるように地域貢献していこうと考えています。
そこで網走建設業協会は、3年前に全道紙である北海道新聞の全道版に、一面を使用してアピール広告を掲載しました。今日の現状で本当に除雪は間に合うのか、救急医療は大丈夫なのかという問題をいくつも提起した内容です。これに室蘭や小樽も続き、全道版やローカル版で同じアクションが起きたのですが、私としては全道的に連動して欲しかったものです。