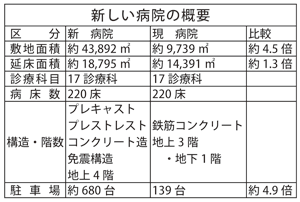建設グラフインターネットダイジェスト
〈建設グラフ2009年4月号〉
ZOOM UP
「緑の樹のような病院」をコンセプトに三沢市立病院が移転新築
――「緑」「命」「育む」が目標
青森県三沢市 三沢市立三沢病院
 |
| ▲完成予想 |
青森県三沢市立病院の移転・新築事業が進んでいる。診療科や病床数は従来と変わらないが、敷地面積は従来の9.739㎡から43.892㎡へと4.5倍、延べ床面積は14.391㎡から18.795㎡へと1.3倍に拡張され、駐車場収容台数も139台分から約680台分の約4.9倍と大幅に拡張され、市民の利便性が飛躍的に向上する。しかも、構造は従来の鉄筋コンクリートからプレキャスト・プレストレストコンクリートへ変更され、免震工法も採用されるなど、構造上の安全性も大幅に改善され、利用する市民にとって安心も確保される。
この新病院建築に当たってのコンセプトは、ハックベリープランに基づく「緑の樹のような病院」(生命力にとみ、大木になる榎)で、これを実現するための目標として「緑」・「命」・「育む」の3つを理念として掲げている。
そこで「緑」の実現に向けては、「早期離床の手助けとなる病院」を目指し、病院を一本の木に喩えて設計されている。癒しの空間と一体感創出のシンボルとなる建物中心部の空間は、木の幹と位置づけてホスピタルアトリュウムを2階まで吹抜け、一部は4階までの吹抜けホールで構成している。それを取り巻く各階の廊下を枝とし、スタッフステーションを経由する各病室を木の葉と位置づけている。
「命」の実現に向けては、「患者様にやさしい病院」を目指し、バリアフリーの導入のほか、現病院で苦情が多かった、診療科や検査部門がわかりにくいといった指摘に対応し、外来患者が受付、診察、検査等から会計までの行程を、一階部分だけで済ませられるよう集中配置している。また入院患者の快適性充実のため冷暖房を完備するとともに、全病室にはトイレ、洗面を設置する。
そして「育む」の実現に向けては「建物の安全性が高く、災害にも強く頼りになる病院」を目指し、地下1階相当部分に地震による横揺れを吸収する装置を取りいれるなど、地震に対して有効である免震構造を採用し、大災害時の緊急救難活動には中心的役割を果たせる構造としている。
このほかにも、ソフト面では、患者の待ち時間短縮などの利便性や、医師・看護師・職員の連携事務のスピード化、管理事務の合理化の実現に向けての検討を続けている。
寄稿
新病院の建設開業に向けて
三沢市立三沢病院長 坂田 優
 |
| 坂田 優 さかた・ゆう |
| 所 属 三沢市立三沢病院 職名 院長 |
| 所 在 地 青森県三沢市中央町4-1-10 |
| 最終学歴 1973年3月弘前大学医学部卒業 |
| 1977年3月弘前大学大学院医学研究科修了 |
| 免 許 等 医師免許 1973年6月収得(218448) |
| 医学博士 1977年3月授与(345) |
| 認定医等 日本癌治療学会評議員・理事 |
| 日本胃癌学会評議員・理事 |
| 日本内科学会認定指導医 |
| 日本消化器病学会指導医 |
| 日本消化器内視鏡学会指導医 |
| 日本老年医学会認定指導医 |
| アメリカ癌学会(ASCO)正式会員 |
| ヨーロッパ癌学会(ESMO)正式会員 |
| がん集学的治療研究財団 評議員 |
| 日本臨床腫瘍学会暫定指導医 |
| がん治療認定医暫定指導医 |
| 勤 務 歴 1977年3月〜弘前大学医学部付属病院医員 |
| 1978年 4月〜三沢市立三沢病院第二内科医長 |
| 1980年 4月〜弘前大学医学部付属病院第一内科助手 |
| 1985年 4月〜弘前大学医学部付属病院第一内科講師 |
| 1992年 3月〜弘前大学医学部第一内科助教授 |
| 1992年 4月〜青森県立中央病院成人病内科部長 |
| 1998年 4月〜青森県立中央病院医療局次長 |
| 弘前大学医学部臨床教授 |
| 1999年 4月〜三沢市立三沢病院 院長 |
| 2008年6月 弘前大学医学部臨床教授 再選 |
| 2011年3月 日本胃癌学会会長 |
| (2009年3月総会にて決定) |
| 専門分野 腫瘍学、消化器病学、血液学 |
| (平成21年2月24日現在) |
|
青森県での地域医療は、主に弘前大学を中心とした医師派遣に依存する自治体病院が担当してきました。三沢市立三沢病院は県内に6つの二次医療圏のひとつである上十三地域の中にあり、面積は香川県とほぼ同等のこの圏域には他に4つの自治体病院があります。当院が担当する医療人口は約14万人となっており、交通の利便性から阻害されている地域という特性から、地域完結型の医療が望まれています。
私は1999年4月に当院に赴任し、これまでの一般医療に加えてすでに勧告されていた「診療機能再編成計画」の骨子に基づき、「がん診療の充実」「循環器疾患の二次治療までの体制の確立」「脳血管疾患の後治療と後方診療体制」そして三沢市を中心とした「地域の医療の完結型診療体制」整備と拡充を順次行ってきました。診療機器の購入はもちろん、当該専門医師の要請から指導医の充実による専門医師の養成を進め、この結果、三沢市立三沢病院における循環器病、特に心臓疾患の診断と治療の充実と進歩、並びにがん化学療法の先端先進的分野では今やいわゆる都会にある「センター」に引けをとらないものと自負しています。 さらには実績が認められて2007年1月には地域がん診療連携拠点病院に指定されました。これまでに取得した様々な学会の指導施設認定をはじめ弘前大学との関連で臨床研修医指導施設にも認可されて、若い医師たちが研修をうけ巣立っていっています。
三沢市のスローガンである「人とまち みんなで創る 国際文化都市」の理念のもとに三沢市立三沢病院は、診療はもちろん学術学問を追究することで数多くの学術論文の発表を行い、さらには院内医誌を刊行して、当院の理念である、質の高い医療と良いサービスを提供し、地域住民から「愛され信頼される病院」をめざしているところです。
また、市民の悲願であった病院の新築移転工事が2010年11月の開院を目指して進められています。新病院は病院職員の創意と総意が結集した現代作品で、歓喜の誕生はもちろん病苦に悩む人々の「癒しの館」であり、神々しく雄大で慈愛に満ちた生命の樹とされる榎が広々と枝を広げてすべてを包み込むHackberry Planとして計画した。完成の暁には、地域住民の健康はもちろん若手医師の養成、さらには専門医の要請にこたえられるものと期待しています。
三沢市立三沢病院 移転・新築工事に貢献します
HOME