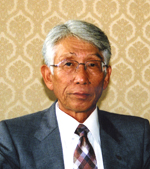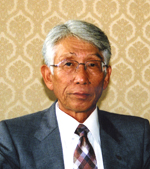建設グラフインターネットダイジェスト
〈建設グラフ2008年10月号〉
interview
昭和40年代から北海道の農業と農業基盤を見続けた三鉱建設
――三井鉱山グループからの新体制へプロパー社長が就任
三鉱建設株式会社 代表取締役社長 三塚 郁夫氏
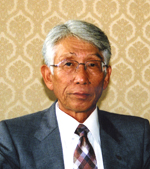 |
| 三塚 郁夫 みつか・いくお |
| 昭和22年11月21日生まれ |
| 昭和41年 3月 美唄工業高等学校土木課 卒業 |
| 昭和41年 4月 三鉱建設株式会社 入社 |
| 平成 2年 4月 同社 土木部長 就任 |
| 平成13年 6月 同社 取締役土木管理部長 就任 |
| 平成17年12月 同社 常務取締役工事管理部長 就任 |
| 平成20年 5月 同社 代表取締役社長 就任 |
| 現在に至る |
|
三鉱建設株式会社
本社)砂川市東1条南18丁目1番31号
TEL0125-52-3111 |
三井鉱山グループを母体とする三鉱建設の社長に、初めてプロパーである三塚郁夫氏が就任した。同グループから独力での経営展開を任されての就任だが、建設業を取り巻く経営環境の荒廃ぶりは周知の通りで、三塚社長も「どう会社を運営していくか、悩みは尽きない」と苦しい胸中を明かす。だが、同社は昭和40年代から農業基盤整備に携わってきた農業土木の老舗でもあり、農家のあり方、農家経営のあり方についても、生産基盤を支える立場から精通している。食の安全が世界的に厳しく問われる情勢下で、北海道の食材は広く注目を集め、テレビのバラエティー番組でも北海道関連の情報が紹介されない日はない。それだけに、北海道の食材の生産を支える農業基盤を担う専門業者は、今後とも重要な役回りを求められている。
- ──三鉱建設の成り立ちから伺いたい
-
三塚 当社の母体は三井鉱山(株)砂川鉱業所でしたが、昭和36年に炭鉱の合理化が行われ、社宅や坑道などの施設の維持管理部門や、設計施工及び土建部門を分離し、それぞれが独立して発足した会社です。
当初は三砂建設の社名でスタートしましたが、38年に三井鉱山(株)芦別鉱業所と三井鉱山(株)美唄鉱業所の土建部門も独立したので、これらを合併し、三つの鉱山の建設部門を総称して三鉱建設に社名変更し、公共工事にも参入しました。
- ──それまでは、三井鉱山関係者のための生産インフラや生活インフラだけに専念してきたわけですね
-
三塚 技術者には土木担当や建築担当、坑道などのトンネルその他、生活インフラにも対応できる技術スタッフが揃っていました。芦別も美唄も上砂川も、すべてが炭鉱城下町で、中心となる企業は一社しかなく、敷地も一社で所有していますから、そこに独力で道路や橋梁などを整備していました。したがって、街そのものを独自に整備していたようなものです。それ以外の区域については、地元自治体が整備しており、住み分けていた格好です。
- ──三塚社長もそれら炭鉱街が出身ですか
-
三塚 私は昭和22年に豊浦町で生まれ、父の関係で奈井江に移住し、美唄工業高を卒業して41年に三鉱建設へ就職しました。いわば、三鉱建設の新卒社員としては一期生となります。
私たちが勤務した頃は、すでに公共工事に参入していましたが、発足して間もなかったために、それほど受注はできなかったので農業土木の分野を目指し、圃場整備や浄水施設などの農業基盤整備へと方向転換していきました。これによって、全道にわたって受注が伸びて、業務を確保できるようになりました。
- ──その頃の農業基盤は、どのような整備が求められていましたか
-
三塚 圃場整備については、大規模化が望まれていました。当時の田圃は一枚が一反にも満たなかったので、それを4〜5反くらいの規模へ再編していました。近年では1〜2町に再編していますが、基本はその頃の規模が基準になっています。昭和40年代に計画された大規模化構想が、現代になって実現している格好です。
工事は田植えと稲刈りの時期を除く春と秋、冬に限られていました。したがって、3月から5月までのわずか3ヶ月の間に150〜200町の整地に当たらなければならず、多忙を極めていました。これにともない、建設重機も大型化していき、バックホーの性能も向上し、今日の建設機械の走りとなりました。それまでは、動力がワイヤー方式で、現代のような油圧方式ではなかったのです。
- ──農業基盤整備には、一般土木と異なる特有の難しさがあると聞きます
-
三塚 そもそも農業土木は、道路や橋梁のような一般土木とは異なり、特定の受益者がありますから、その要望を的確に捉えて満足できる良いものを作らねばなりません。そのため、受益者と的確にコミュニケーションしなければならず、それが欠けると良いものはできません。他人様の財産に手を加えるのですから、やはり完成した後の収穫状況も心配になります。
- ──そのために長年にわたって農家と交流してきたものと思いますが、近年の農家は変わってきましたか
-
三塚 かなり変わりました。昭和40年代の農家は機械力が無く、都市部と違って流行に触れる機会も少なく、経済的にも地域格差がかなり大きかったのです。そのため農村の共同体意識が強かったのですが、近年はそれが稀薄になっています。営農規模が拡大し、大規模化しているので、会社形式で運営しているところもあり、かつてのような隣組で協働しようという傾向が見られなくなってきました。
もっとも、共存共栄のコミュニティが失われているのは、農村部に限ったことではありませんが、機械化が進む一方で、淘汰される農家も現れている状況ですから、これから参入しようという人は、ある程度の規模に抑え小規模多品種で営農した方が良いと思います。そうすれば様々な外圧に対しても、主力作物を柔軟に変更するなどで対抗していけるでしょう。
- ──空知管内は北海道の米所ですが、かつて北海道米は下級米に分別されていました。しかし、最近になってようやく評価が高まりましたが、米農家や関係者の努力の賜ですね
-
三塚 道産米の消費が大きく拡大してきているのは嬉しい傾向で、その基盤整備を担った者として誇りが持てます。特に空知の経済は農業が中心となっていますから、これが後退したのでは私たちも存続できません。空知は農家がいて、その土壌を作る私たち建設業があって成り立っています。特に、管内の土木は8割以上が農業土木ですから。
ただし、そうした営農環境を守る上では、治山にももう少し力を入れて欲しいものです。最近になって、環境が山から海まで繋がっていることが、改めて認識されるようになりましたが、山地の植樹によって海の生態系を守るという知識と技術は、そもそも古くからあったのです。それらを切り離して管理してきたために、全体のシステムのバランスが崩れたのだと思います。
- ──そうした農業と農業土木の変遷を見続け、いよいよ今年から初代のプロパー社長として就任しましたね
-
三塚 この4月に就任しました。会社も新体制で進むことになったことから、3月に就任の打診があり、かなり悩みました。それまでは、社長職には三井鉱山グループから就任していましたが、そろそろ独力でやってはどうかとの後押しがあったわけです。
就任してから挨拶回りをしましたが、「おめでとう」と祝福される一方で、「こんな厳しい時期に、何を考えているのか」と言われたこともありました(笑)しかし、新体制となったお陰で、従業員達も自分なりの目標ができたことから、かなり自発的に頑張ってくれています。
ただ、建設業を取り巻く経営環境は大きな変革の時期にありますので、どのように会社を先導していくべきか、悩んでいます。業界のあり方の問題があり、さらにその中での当社の位置づけの問題もあります。
長らく農業土木に携わってきた実績に対する自負は、私も職員もみな持っていますが、建設産業の流れがどこへ向かうのかを見極め、私たちの立つべき位置を考え、何をしていくべきかを見定めなければならないでしょう。それによって、48人の社員とその家族を守っていかなければならず、それができてこそ地域社会に対して責任を果たせたと言えるのだと思います。
中には、新規事業参入への勧誘もあるのですが、異業種に新規参入していった事例を見る限りは、99パーセントが失敗しています。農業土木に携わってきた建設会社なら、農業に参入しやすいものと思われがちですが、農業と建設業は経営ノウハウが全く異なります。敢えて農業で成功するには、相当の時間をかけなければなりませんが、それは時間的にも資産的にもかなり難しい課題だと思います。
したがって、今後とも本業に徹することに変わりはないですが、99パーセントが官庁工事ですから、予算カットの影響はもろに受けます。そうしたことからも、異業種への新規参入の努力は続けなければなりません。収入を得るには絶対に競争に勝たなければならないので、勝算さえあれば、参入によって業務の幅が広がるため、できることなら参入したいものです。
- ――やはり本道の建設産業そのものの再生が必要ですね
-
三塚 いかに世論の批判があろうとも、北海道経済は一次産業と建設業が中心で、地元に影響力を持つ業界が崩壊すれば、地域経済にかなりの悪影響も出ます。それぞれが経営の基盤を整備するなかで、各地域が抱える共通の課題を解決しなければ経済構造は変わりません。そうした努力が、各業種、各地域で続けていかなければならないと思います。
- ──自給率の高い北海道は、食糧供給基地を自任していますが、その土台は建設業界が支えていますからね
-
三塚 ただし、現在の農政をそのまま続けていく限りは、北海道は食糧供給基地にはなり得ないと私は感じます。農業政策というものをもう一度、整理して見直す必要があると思います。
例えば、米の単価はひたすら下がり続けており、その生産を支える基盤整備への補助も、これは農家負担が伴うものですが、補助率の動向が不透明です。それらも含めて、農家経営がどうすれば成り立っていくのか、その経営基盤を見直し、農家に意欲を持たせることから再スタートする必要があると思います。そうした農政の進め方次第で、北海道の農業はより一層の発展を見ることができるのだと思います。
| 会社概要 |
| 創 立:昭和36年2月 |
| 資 本 金:1億円 |
| 社 員 数:46名 |
支店・営業所:札幌支店、上砂川支店、美唄支店、道東営業所
|
許可・業種:北海道知事許可(特-18)室 第132号
・土木工事業
・建設工事業
・とび・土工工事業
・電気工事業
・鋼構造物工事業
・舗装工事業
・造園工事業
・水道施設工事業 |
|
三鉱建設株式会社ホームページはこちら
HOME