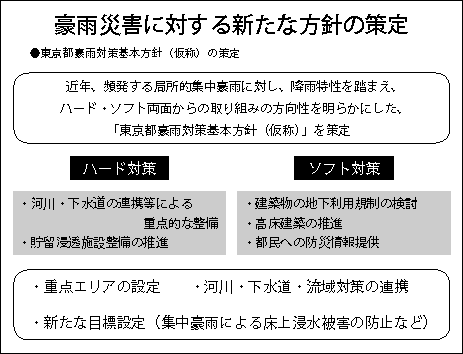建設グラフインターネットダイジェスト
〈建設グラフ2006年8月号〉
INTERVIEW
河川水位や雨量の提供で水害から都民を守る(後編)
安全・安心のまちづくりと水辺の魅力向上への取り組み
東京都建設局 河川部長 野村 孝雄氏
 |
| 野村 孝雄 のむら・たかお |
| 昭和 | 47年 | 3月 | 京都大学交通土木工学科修士課程修了 |
| 昭和 | 47年 | 4月 | 東京都採用 |
| 昭和 | 63年 | 4月 | 第三建設事務所工事第一課長 |
| 平成 | 4年 | 4月 | 都市計画施設計画部施設計画課長 |
| 平成 | 7年 | 9月 | 第六建設事務所副所長兼工事課長 |
| 平成 | 11年 | 6月 | 株式会社ゆりかもめ建設担当部長 |
| 平成 | 12年 | 8月 | 港湾局離島港湾部長 |
| 平成 | 16年 | 8月 | 建設局企画担当部長 |
| 平成 | 17年 | 7月 | 建設局河川部長 |
|
梅雨前線の発達による豪雨で、九州大分方面で地盤が崩壊し、全国的に驚愕のニュースとなっている。それは、全国に共通する多雨多湿の列島の気候として、他人事ではないからであり、昨年に浸水被害を受けた東京都にとっても同様である。東京都では、地下河川による水害管理の実績と可能性から、今後もその拡大整備に取り組む考えだが、同時に管理された河川は、さらに親水機能を持たせることで、観光資源としての有効活用も可能だ。前号に引き続き、野村孝雄河川部長に、豪雨浸水対策とも多面的な河川利用の方向性などを伺った。
- ――豪雨時のソフト対策について具体的にお聞きしたい野村
-
まず浸水危険情報の提供、すなわち浸水予想区域図の作図・公表ですが、都の場合は、東海豪雨を予測対象の降雨規模として順次進めて来ています。もう間もなく、中川・綾瀬川流域を公表する予定にしていますが、これで区部はすべて公表ということになります。この浸水予想区域図を元に区市町で避難場所などの情報も付加したハザードマップを作ることになっており、都内の多くの自治体で公表が進んでいます。
次に雨量・水位情報の提供です。都では「水防災総合情報システム」として雨量計138ヶ所、水位計149ヶ所の観測情報を1分単位で更新しながら、水防管理団体に提供しています。
この情報はインターネットや携帯電話で一般の都民の方々にも提供しています。平成14年から開始していますが、年々アクセス数が増加しており、都民の関心の高まりが伺えます。今後は水位予測のシステムを確立したいと考えており、神田川水系で予測精度の検証を進めています。
- ――治水対策が何よりも最重要課題ではありますが、近年では河川の多角利用も求められていますね
野村
-
河川行政への要望は、親水機能の強化など、確かに多様化してきています。それに応えるため、隅田川(浅草・両国)や、江東内部河川、運河を中心に、水辺の賑わいを創出し、美しい水辺景観の形成、アクセスや水環境の改善を推進し、魅力的な都市空間を創造していく方針です。
特に外国人観光旅客も視野に入れて、浅草・両国地域の広域的な観光まちづくりの推進組織を支援し、地域の伝統産業・文化を体験できる観光交流拠点の整備や、観光ボランティアの育成を進めていく予定です。
また、隅田川のテラスについても、誰もが快適に水辺を利用できるよう、連続化やバリアフリー化を進めます。そして、地域と連携しながら堤防壁面をギヤラリーとして開放し、親しみやすい空間づくりを進める考えです。
一方、江東内部河川地域における取り組みとしては、江戸時代に「塩の道」であった小名木川を、江戸情緒を醸し出す水辺空間として整備すると同時に、扇橋閘門に見学施設を整備し、治水機能に加え、観光資源として活用を図ります。
- ――建設局以外でも関連した取り組みがありますか
野村
-
運河地域においては、これは、港湾局の取り組みになりますが、「品川浦・天王洲」、「芝浦」で取り組まれている運河ルネッサンスの広域展開を支援し、運河地域の賑わいや魅力を創出します。
さらに、水辺活用マニュアルの作成により、テラスや船着場の利用ルール、通航できる船の大きさ・高さ等を紹介し、水辺の利用を容易にしていきます。
一方、船による周遊の視点も加えた水辺の広域観光マップ作成、観光案内標識の整備、水辺イベントの連携など、多様な方法で東京の水辺の魅力を発信していくこともオール東京都の観光施策として考えられています。
また、せっかく親水空間を創っても、河川水が汚染されていたのでは興ざめですから、合流式下水道の改善や高度処理事業の推進により、河川や運河の水質の向上を図ることも重要でしょう。
- ――少し戻りますが、治水整備の中で、近年、特に注目されているのは地下調節池でしたね
野村
-
すでに都道環状七号線地下調節池がほぼ概成しており、使用開始しています。
河川沿いに住宅等が密集している区部では、下流から順次用地を買収し、拡幅を行う通常の整備では、中上流部の護岸を整備するまでに相当な期間を要してしまいます。
このため、中上流部における水害の早期軽減を図るために、調節池や分水路など洪水を上手にコントロールする施設整備を行ってきました。
環状七号線地下調節池は、都道環状七号線下の公共空間を利用してトンネルを建設し、ここに神田川等の洪水を貯留するものです。トンネルは延長4.5km、内径12.5mで、貯留量は54万m3となります。
平成16年9月の台風22号の際は、貯留能力24万m3(第一期工事分)の90%である21万5千m3を流入させることにより、浸水被害を大幅に減少させました。
また昨年9月4日の集中豪雨では、第一期工事分が初めて満杯になり、急遽、事業中だった第二期工事分にも貯留し、浸水区域の拡大を防止しました。
- ――2回にわたりお話を頂きありがとうございました
野村
-
今後とも治水と併せ、河川空間の利用等の取り組みを進めて行きたいと考えております。
HOME