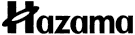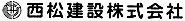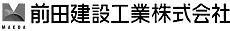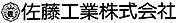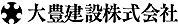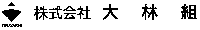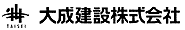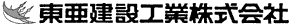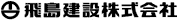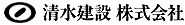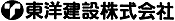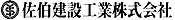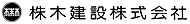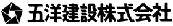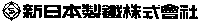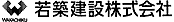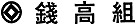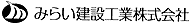新若戸道路の施工にあたって
| ●新若戸道路陸上トンネル部本体築造工事(若松側) | |||||||||
| 間・西松・前田建設工事共同企業体 新若戸作業所長 宮原 孝平 | |||||||||
|
当工区は、新若戸道路(港湾整備事業:1,181m)のうち、若松側沈埋函接続部に位置する陸上トンネル区間120mの2連ボックスカルバート(幅:約36m,高さ:約11m)を鋼管矢板土留め壁による開削トンネル形式で築造する。開削部は、護岸から延長約150m、幅約40m、深さ約15~20mの掘削である。工事場所は、洞海湾に面した埋め立て地で周囲は精密機械や天井走行クレーンを有する工場が隣接し、開削工事に伴う掘削部の安全性確保とともに周辺の地下水位低下や地盤沈下が重要な課題であった。 施工に当たっては、工事の安全性及び沿道工場への影響把握から、各種の計測機器を配置しその計測管理下で行った。その結果として、土留め壁施工時の遮断壁(smw壁)、本体掘削前の精密機械基礎の改造、支保工撤去に伴う土留め壁変位対策としての構築内盛替え支保工の増設(一部コンクリートスラブ)等実施した。また、当初難透水層と考えていた鋼管矢板根入れ岩盤部に強風化の破砕帯が脈状に分布することが判明し、盤ぶくれ対策が必要になり、底盤(岩盤)改良、ディープウエル、リチャージウエル等の対策を行った。これらの対策により、工事の安全性が確保でき、沿道工場への影響も最小限で抑えれたものと考えています。現在、躯体・仮設工事もほぼ終わり3月末の竣工に向けて仕上げ工事を行っています。発注者を始め関係機関のご指導と沿道工場の協力に感謝するとともに、今回の貴重な経験を今後の工事に生かしていきたいと思っています。 |
|||||||||
|
|||||||||
| ●新若戸道路擁壁部本体築造工事(若松側) | |||||||||
| 鹿島・佐藤・大豊特定建設工事共同企業体 工事事務所長 梶栗 福留 | |||||||||
|
新若戸道路は、若松側陸上掘割部をニューマチックケーソン4函で構築します。当jvは、そのうちの海側2函を担当しています。 工事は、面積1500㎡のケーソンを2.5mの間隔に1函ずつ、深度15mまで沈設するもので、特にその着底盤がn値2~3の軟弱な沖積粘土層である点が特徴です。 工事を進めるに当たり次の点に配慮しています。①安全:ケーソン周りに仮設用地が十分に確保できず作業の多くが輻輳するため、隣接工区を含めた連絡調整を密に行っています。躯体構築をはじめほとんどが高所作業ですので、その足場・設備は災害要因を極力排除できるようなものにしています。②品質・出来形:コンクリートはマスコンになるため、温度応力解析に基づき低熱セメントや誘発目地を採用し、ひび割れ指数1.2以上を確保しています。躯体の止水は、沈設前に吹付防水を行うほか、打継面はグリーンカットによるレイタンス処理、止水ゴムの設置を行っています。沈下掘削に当たっては、油圧ジャッキによる圧入を併用して沈設精度を上げ、沈設最終段階では計測データに基づいた掘削管理を十分に行い過大な沈下を抑制します。 現在、進捗は約60%です。来年度の竣工に向けて安全に工事を進めて参ります。 |
|||||||||
|
|||||||||
| ●新若戸道路擁壁部本体築造工事(若松側)(第二次) | |||||||||
| 大林・熊谷・不動特定建設工事共同企業体 工事事務所長 大久保 政吉 | |||||||||
 新若戸道路建設工事の整備計画では、北九州市洞海湾横断部の沈埋トンネル区間を挟み、戸畑側と若松側の陸上部にトンネル区間と掘割区間が設けられている。当工区は、若松側のニューマチックケーソン区間のu4、u5の2函体とアプローチ部を合わせた、延長109mを担当している。ケーソンの規模は約1,500~1,700㎡と、道路用ニューマチックケーソンとしては最大級の施工面積を誇る。又隣接する工場への影響を最小限にとどめる為、沈設に際しては既設構造物の変動に細心の注意を払う必要がある。その為、ケーソンの施工に先立ち隣接工場との境界部にsmwによる縁切壁を造成し、各計測機器を設置の上、情報化管理により躯体への作用力と姿勢、及び周囲の挙動をリアルタイムに測定し沈設を行っている。ケーソンの沈設深さは約14mと浅いが、一旦沈設誤差が発生すると修正は困難となる。その為圧入アンカーの併用により高い精度でのケーソン沈設を目指している。ケーソン沈設後もケーソンの接合部の施工等与えられた課題は数多くあるが、技術力と組織力を駆使して解決し、無事竣工を迎えられるよう現場一丸となって品質と安全を第一に心掛けて工事を進めて行きます。 新若戸道路建設工事の整備計画では、北九州市洞海湾横断部の沈埋トンネル区間を挟み、戸畑側と若松側の陸上部にトンネル区間と掘割区間が設けられている。当工区は、若松側のニューマチックケーソン区間のu4、u5の2函体とアプローチ部を合わせた、延長109mを担当している。ケーソンの規模は約1,500~1,700㎡と、道路用ニューマチックケーソンとしては最大級の施工面積を誇る。又隣接する工場への影響を最小限にとどめる為、沈設に際しては既設構造物の変動に細心の注意を払う必要がある。その為、ケーソンの施工に先立ち隣接工場との境界部にsmwによる縁切壁を造成し、各計測機器を設置の上、情報化管理により躯体への作用力と姿勢、及び周囲の挙動をリアルタイムに測定し沈設を行っている。ケーソンの沈設深さは約14mと浅いが、一旦沈設誤差が発生すると修正は困難となる。その為圧入アンカーの併用により高い精度でのケーソン沈設を目指している。ケーソン沈設後もケーソンの接合部の施工等与えられた課題は数多くあるが、技術力と組織力を駆使して解決し、無事竣工を迎えられるよう現場一丸となって品質と安全を第一に心掛けて工事を進めて行きます。 |
|||||||||
|
|||||||||
| ●新若戸道路陸上トンネル部本体築造工事(戸畑側) | |||||||||
| 大成・東亜・飛島特定建設工事共同企業体 現場代理人 田中 信博 | |||||||||
|
本工事は、新若戸道路の港湾整備事業区間1,181mのうち、戸畑側陸上アプローチ部の延長約100m区間を開削し、内空断面、幅2×9.90m、高さ8.0mの2連ボックスカルバートを築造するものであります。 施工場所は陸上部とはいうものの、周りは洞海湾に囲まれているため、地下水(海水)の供給は無限であり、開削工事における止水対策工および根入れ部の安定問題(軟岩部の断層および破砕部からの漏水による盤ぶくれ対策等の必要性の有無)、構築開始時から完成時に至るまでに懸念される軟弱粘土層の圧密沈下による躯体への影響の検討が必要となります。 また、近接構造物(燃料タンク等)が存在しており、沈下計、傾斜計等による動態観測を行い、近接構造物への影響の把握を行っています。 平成18年2月現在、50%の進捗状況です。4月からは、ボックスカルバートの構築が本格的に始まります。平成20年2月の工事完成に向けて、発注者、他工区との連携を取りながら工事完了まで全員気を引き締め、無事故・無災害で乗り切る所存です。 |
|||||||||
|
|||||||||
| ●新若戸道路擁壁部本体築造工事(戸畑側) | |||||||||
| 清水・りんかい日産・奥村特定建設工事共同企業体 所長 本島 誠也 | |||||||||
|
本工事は、新たに洞海湾を横断する臨港道路『新若戸道路』工事の内、戸畑側擁壁部(沈埋トンネルへのアプローチ部分)l=171.7mを施工するものです。主要工事内容は、土留工(ケーシング回転掘削:φ1,500,
延べ4,200m, smw工:φ600~550, 5,000㎡)、開削工(掘削:28,500m3,
埋戻し:流動化処理土4,400m3, 再生クラッシャーラン1,300m3)及び本体工(躯体コンクリート:6,500m3,鉄筋900t)です。 施工場所は、食品等の工場群及び物流倉庫群に近接している為、特に重機械の振動・騒音及び第三者・交通関連災害に留意して施工する必要があります。現在の工事進捗率は約7%で、土留工の内ケーシング回転掘削工の施工中です。 本工事の工期は、約30ヶ月と長期間となりますが、無事故無災害で竣工を迎えられるよう作業所一丸となって安全に工事を進めてまいります。 |
|||||||||
|
|||||||||
| ●新若戸道路仮航路(-9m)外1件浚渫工事(若松側) | |||||||||
| 東洋・佐伯・株木特定建設工事共同企業体 響灘作業所長 塩崎 和行 | |||||||||
|
本工事は、現在建設が進められている新若戸道路の第一期(港湾施工部分)における、施工のための仮航路の浚渫と沈埋トンネル部のトレンチ浚渫(溝掘)を施工するものである。 仮航路土砂内部には油分が含有することが確認されており、周辺環境に配慮した施工が必要なため、油混じり土砂浚渫については、密閉式のグラブバケットを使用し、水中での油分拡散の抑制に配慮を行い、土運船は、船倉上部に密閉蓋を設置して周辺への油臭の拡散を防止し、浚渫により発生した土運船内の余水(上水)は、油分が含まれているため、余水処理を実施している。土砂については、固化処理機によりセメント固化させた後に、ガット船(運搬船)に積み替えて、再資源化処理施設に搬入し、再資源化処理施設においては、焼成(約1000℃)処理を行い、建設材料などに利用可能な土砂にリサイクルを実施している。 また、トレンチ浚渫での床掘土砂は、土運船(密閉式)で揚土個所に運搬し、リクレーマ船を用いて揚土し、北九州市が建設を進める埋立地内に陸上運搬し土捨処分している。 両浚渫とも施工に当たっては、浚渫時は周辺海域に対する濁り拡散防止対策として、グラブ式浚渫作業船首に海底面に達する膜を装着した汚濁防止枠を使用し、水質の汚濁防止を図っている。 現在は、油混じり土砂の撤去が周辺環境へ影響を与えることなく完了し、沈埋トンネル部のトレンチ浚渫の施工を推進しており、平成18年3月の竣工を、無事故無災害で迎えられるよう職員一同取り組んでいる。 |
|||||||||
|
|||||||||
| ●新若戸道路沈埋トンネル部(1号函)製作工事 | |||||||||
| 五洋・新日鐵・若築特定建設工事共同企業体 工事所長 玉井 昭治 | |||||||||
|
本工事は新若戸道路の内、海底トンネル部にあたる沈埋函(全7函:557m)の1号函(幅27.9m×高さ8.4m×長さ106m)の製作を行うものです。工事の手順として、まず陸上の製作ヤードで、鋼殻ブロックの製作・大組立および艤装品の取付を行います。完成した鋼殻は岸壁へ移動させた後、海上へ進水させて係留桟橋まで曳航・係留します。鋼殻が浮遊した状態で、本体コンクリ-ト(約8,700m3)を打設し、保護コンクリ-ト、道床コンクリ-トにより乾舷を調整します。その後、仮置に必要な艤装を行い、仮置マウンドまで曳航し、仮置を行って工事完了です。 本工事の特徴は、以下に挙げる新技術の採用であります。①ゴムガスケットに伸縮性止水ゴムを採用、②本体コンクリートに充填コンクリートを使用、③鋼殻係留時に防舷材式緩衝装置を使用、④鋼殻進水で大型起重機船による一括吊上げ方式を採用。これらの沈埋函製作に導入された新技術、新工法を有効に活用し、工事の安全施工に努力していきます。 |
|||||||||
|
|||||||||
| ●新若戸道路沈埋トンネル部(2号函)製作工事 | |||||||||
| 東亜・錢高・みらい特定建設工事共同企業体 所長 山田 治男 | |||||||||
|
新若戸道路は、ひびきコンテナターミナルの整備に伴い、響灘地区と戸畑、小倉方面を接続するための臨港道路として計画されており、洞海湾を横断する海底トンネル部は、沈埋トンネル工法が採用されています。 当工事は、沈埋トンネル部(全7函)のうち、2号函の鋼殻製作、回航、本体工及び仮置工等を行うものです。 2号函製作工事の特徴としては、函体を内外面鋼殻で製作後、内部に充填コンクリートを打設し、一体化する構造(フルサンドイッチ構造)を採用し、狭隘部での鉄筋組立作業を不要にしていること。鋼殻は三井造船大分事業所製作ヤードで製作し、完成後、台船に積み込み、北九州港まで回航し、台船を沈降させて進水させる工法をとっていること。加振併用型充填コンクリートを使用し、必要な充填性を確保しつつも低コストを実現していること。また、伸縮性止水ゴムを採用し、沈設後の方向修正を省略できる構造としていることが挙げらます。 現在、鋼殻製作工事が始まり、平成18年9月頃に大組立が完了する予定です。鋼殻の回航、進水時期は、台風期にあたりますが、的確な気象予測、避難場所の確保等、発注者や関係機関と連携を取り合い、無事竣工が迎えられるよう職員一丸となって取り組んでいきます。 |
|||||||||
|
|||||||||