 |
| ▲第三海堡の撤去作業 |
ZOOM UP
特集・港湾新時代〜世界の港湾立国へ〜 |
| ▲第三海堡の撤去作業 |
 |
 |
|
| ▲第三海堡復元図 | ▲関東大震災直後の第三海堡 |
 |
 |
|
| ▲第三海堡の復元模型(被災直後) | ▲第三海堡の復元模型(被災直後) |
 |
 |
|
| ▲第三海堡付近を航行する 大型船舶 |
▲第三海堡に座礁した貨物船 |
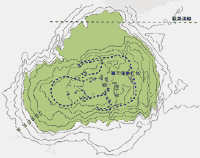 |
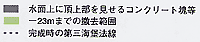 |
| ■浦賀水道航路(第三海堡の撤去) |
| 撤去前〜暗礁化した第三海堡により浦賀水道航路の難所になっています。 |
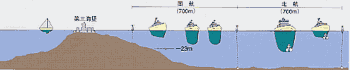 |
| 撤去前〜第三海堡の撤去により必要水深が確保され、船舶が安心して航行できます。 |
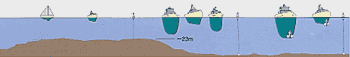 |
 |
 |
|
| ▲コンクリート塊 | ▲コンクリート塊 |
[資料]
東京湾海堡の使用材料と工事費 費用(円) 石材(m3) 砂(m3) 人夫(人) 石材 埋填砂 諸材料 職工・人夫 計 第一海堡 73,264 129,385 316,776 172,947 25,230 69,256 110,872 378,805 第二海堡 485,968 299,243 495,855 296,796 92,107 154,816 247,928 791,647 第三海堡(予定) 2,781,864 540,816 435,290 1,795,415 239,365 197,743 261,174 2,493,697 合計 3,341,096 969,444 1,247,921 2,265,176 356,702 421,814 619,973 3,663,649
『東京湾海堡基礎築設方法及び景況取調所』
明治39年8月より作成
[註]1)工事費は埋め立て造成費のみで、大砲などの兵備費は含まない。
2)第一海堡は、明治14年〜20年までの実績額
第二海堡は、明治22年〜32年までの実績額
第三海堡は、明治25年〜40年3月までの予定額
第三海堡地区安全衛生連絡協議会
環境調査 項目 調査項目 調査頻度 備考 流況 流向、流速 工事着工前及び完了後の夏季と冬季にそれぞれ1回 工事前後の流況の変化を調査します 水質 生活環境項目(PH、DO、COD等)
栄養塩類(全窒素、全りん)健康項目等工事施工中から完了後3〜5年
までの各年(2〜4回)定期的に水質調査を実施し、
工事施工中から完了後までの水質変動を調査します。底質・
海生生物底質:粒度組成、強熱減量、
全硫化物等
海生生物:工事による影響を受け
る可能性がある底生
生物及び魚介類工事施工中から工事完了後の生物相が安定すると
考えられる3〜5年までの各年(2〜4回)定期的に調査を実施し、工事施工中から
完了後までの底質及び海生生物の出現状況の
変動を調査します。