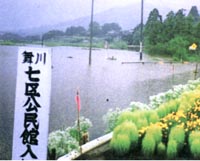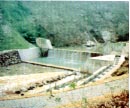| 佐藤 宏明 さとう・ひろあき |
| 生年月日 昭和31年3月18日生 |
| 出身地 北海道帯広市 |
| 最終学歴 北海道大学大学院 |
| 昭和 55年 4月 北陸地方建設局富山工事事務所採用 |
| 昭和 57年 4月 宮城県河川課へ出向 |
| 昭和 59年 4月 河川局開発課係長 |
| 昭和 61年 4月 関東地方建設局宮ヶ瀬ダムエ事事務所調査設計課長 |
| 昭和 63年 1月 関東地方建設局河川部河川調整課長 |
| 平成 元年 7月 関東地方建設局河川部河川計画課長 |
| 平成 2年 4月 本省河川局河川計画課長補佐 |
| 平成 4年 7月 東北地方建設局胆沢ダム工事事務所長 |
| 平成 7年 4月 東北地方建設局企画部企画調査官 |
| 平成 9年 4月 (財)ダム水源地環境整備センターヘ出向 研究第三部長 |
| 平成 11年 4月 現職 |