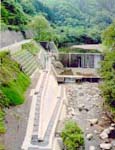〈建設グラフ2001年2月号〉
寄稿
自然と調和した砂防事業を
国土交通省 中部地方整備局 越美山系砂防工事事務所長 田井中 治 氏
 |
田井中 治 たいなか・おさむ
| 昭和 59年 |
京大林学科(砂防学研究室)卒 |
| 昭和 59年 |
建設省入省 |
| 昭和 59年 |
秋田県土木部砂防課技師 |
| 昭和 61年 |
建設省中部地方建設局多治見工事事務所
砂防調査課 調査係長 |
| 昭和 63年 |
林野庁指導部地すべり係長 |
| 平成 2年 |
建設省東北地方建設局福島工事事務所
調査第一課長 |
| 平成 4年 |
建設省九州地方建設局河川部 建設専門官 |
| 平成 6年 |
建設省土木研究所砂防部地すべり研究室
主任研究員 |
| 平成 8年 |
日本道路公団技術部道路技術課 副参事 |
| 平成 10年 |
建設省建設経済局建設振興課労働・資材対策室
課長補佐 |
| 平成 12年 |
建設省中部地方建設局越美山系砂防工事事務所
所長 |
|
流域の概要
木曽三川の最も西に位置する揖斐川は、その源を岐阜県揖斐郡藤橋村冠山、釈迦嶺、高倉峠あたりの小さな谷川に発し、安八郡神戸町地先で、本巣郡根尾村能郷白山を源とする根尾川を合わせ濃尾平野を南流し、三重県桑名市地先で長良川と合流、伊勢湾に注いでいます。その流域面積は約3,880平方キロメートル(うち揖斐川本流約1,840平方キロメートル)に及びます。
当事務所が担当する直轄砂防事業は、揖斐川上流域867.9平方キロメートル(揖斐川本流の流域面積の約半分)で、岐阜県揖斐郡坂内村・藤橋村・久瀬村及び本巣郡根尾村の全域です。
流域の地形は、揖斐川は北西面を標高1,300m級の越美山地によりさえぎられ、急勾配の渓流が多くあります。地質は、全体に秩父古生層で占められ、揖斐川の花崗岩・泥質混在岩、根尾川の砂岩・粘板岩の互層に大別されます。
また、流域内には、明治24年(1891年)濃尾地震(震源地は根尾村水鳥(みどり))の発生した根尾谷断層等の活断層が多数分布し、脆弱な地質となっています。
事業の概要
昭和43年の事業着手以来、荒廃地域からの土砂流出防止、多目的ダムヘの土砂流入抑制及び土石流危険渓流での土砂災害防止等の事業を推進しています。また、活力ある地域づくりを支援する砂防事業と合わせて、自然と共生を図る砂防事業との推進を図り、平成11年度末までに126基の砂防施設、8ヶ所の魚道を整備してきました。
それとともに、近年要望が高まっている環境対策についても、「水とみどりと人のハーモニー」を合言葉に、自然環境や人々のふれあいを大切にし、土砂災害から生活を守りながら、より豊かな環境を作ってゆくことがこれからの「砂防」の仕事だと考えています。
事務所の概要
揖斐川流域の直轄砂防事業は、昭和2年に根尾川において着手され、第二次世界大戦により事業を中断したまま、昭和26年にそれまでに完成していた砂防設備を岐阜県に移管しました。
昭和40年9月台風24号に伴う前線の集中豪雨により、揖斐川上流域、真名川流域は、未曽有の災害にみまわれました。国土交通省は、昭和43年越美山系砂防工事事務所を設置し揖斐川上流の横山ダム(昭和39年完成)の上流域の揖斐川本川・坂内川及び根尾川上流根尾西谷川・根尾東谷川合流点(根尾村樽見)上流域で直轄砂防事業に着手しました。その後、平成元年9月6日〜7日にかけての秋雨前線豪雨により、揖斐川本川中流域及び根尾川において集中豪雨があり、災害が発生しました。
このため、平成元年度に直轄砂防事業区域を藤橋村・久瀬村及び本巣郡根尾村の全域に拡大し、土砂災害対策を実施しています。
事業展開方針
-
1.横山ダムの治水機能の維持
2.下流河川の河状安定
3.人家・公共施設に対する直接的な土砂害の防止
4.横山ダム、徳山ダム等河川総合開発計画との協調
-
具体的には、
(1)豪雨等により荒廃した流域の復旧、過去の大災害による重荒廃地およびh元災害箇所の復旧
(2)土石流・流木対策施設の整備
未着手の土石流危険渓流、H10流木災害箇所および災害弱者対策を優先
(3)大規模崩壊による天然ダム形成、決壊に対する予防および被害の軽減化情報基盤整備等による危機管理体制の整備等
(4)森林の持つ治水機能の低下を防止
1)人工林の荒廃を防止するため、安全に人が生活できる環境づくりを支援する砂防事業の推進
1.地域活性化を支援する砂防施設の整備
例:ナンノバイクランド(床固工)、遊ランドスキー場・貝月スキー場(流路工)等
2.住環境、自然環境に配慮した砂防施設の整備
例:人工の滝を創出した砂防ダム、現地採取自然石を用いた砂防ダム・流路工、
魚道の設置、緑の砂防、水辺の学校(床固工)等
2)面的砂防の検討
(5)総合土砂管理対策(止める砂防・流す砂防)
(6)横山ダム堆砂対策事業との計画分担
揖斐川上流域の渓流環境整備計画「基本理念」
1.災害防止と渓流環境保全のために、自然と調和した安全な渓流空間を創造します。
揖斐川上流域は、豊かな自然に恵まれていると同時に、根尾谷断層、ナンノ谷崩壊地、徳山白谷崩壊地、根尾白谷崩壊地等にみられるように、一つの大雨で大量の土砂が流出する危険性をもっています。したがって、災害防止とよりよい渓流環境の創造のために、自然になじんだ砂防設備を積極的に整備します。
2.生態系に配慮した渓流を創造します。特に、魚がすみやすい渓流を創造します。
揖斐川上流域は、太平洋側にみられるものと日本海側にみられるもの、暖地性のものと寒地性のもの等、多種多様の動植物が生息しています。さらに、河辺の植物群落がヤマセミ等の鳥類やムカシトンボ等の昆虫の生息場所となっており、渓流と生態系が調和した豊かな空間が多く存在します。
これらの優れた生態系に配慮し、次代に伝えるにふさわしい渓流を創造します。また、揖斐川上流域には、アマゴ、アユ、アジメドジョウ等の多くの渓流魚が生息しています。魚道の設置、瀬と淵の保存、再生、創出をはかり、魚がすみやすい渓流を創造します。
3.景観、文化に配慮し、渓流とのふれあいの場を創造します。
揖斐川上流域は、景観に優れた渓流や渓谷が多く見られるとともに、夜叉が池伝説、猿楽狂言等の無形文化財等が継承されています。これらの優れた自然と文化に配慮した水辺空間を創造するとともに、多くの人々が豊かな自然とふれあうことができる渓流を創造します。
●本計画で用いる「保全」、「創造」及び「渓流の利用」の概念は、以下のような概念とします。
「保全」とは、自然環境・景観の質を現在の状態に保つことである。
現在の状態に保つための考え方には、全く手を付けない、あるいは適正な維持管理をするという考え方とともに、一時的にあるいは短期的に現在の状態を損なうことがあっても、もとの状態に戻す(自然あるいは人為的に)という考え方も含めるものとする。
「創造」とは、現在の自然環境・景観を新たに良好な状態に創り変えることである。新たな状態に創り変える為の考え方には、本来あるべき姿に戻す、将来的には周辺と調和した状態にするという考え方とともに、人間の社会活動にとって利用しやすい状態にするという考え方も含めるものとする。
「渓流の利用」とは、自然環境に留意しつつ、人間活動の場として、渓流及び渓流周辺の利用・活用を図ることをいう。
「渓流の利用」とは、自然環境に留意しつつ、人間活動の場として、渓流及び渓流周辺の利用・活用を図ることをいう。すなわち、渓流及び渓流周辺の自然、社会、文化的な状況に配慮しながら、レクリエーション、散策、自然観察、文化的活動等の一般の利用に供するという考え方である。
揖斐川流域の三大崩壊地
1895年(明治28年)8月5日坂内村川上ナンノ谷、1965年(昭和40年)9月14日〜17日徳山白谷、根尾白谷で大きな山崩れが発生しました。この三大崩壊は、1891年(明治24年)10月28日の濃尾大地震とその後の集中豪雨等によって地盤がゆるんだことが一つの要因だと考えられています。
根尾村大須地区「水とみどりの渓流学校構想」
その特徴は、
■渓流沿いに多自然な砂防空間を創造します。
多自然な空間の中身は、「砂防の森」「ビオトープ」「魚が棲みやすい流れ」などで、いざという時には土砂を堆積させ、いつもは渓流沿いの自然が楽しめる多自然な空間を造ります。
■小学校跡を利用した自然学習塾(学校)を整備します。
小学生をはじめ来訪者には、渓流周辺の自然の楽しみ方や砂防の役割などについて、説明や学習の手助けをし、砂防の森づくりには、地元の方を含め、広く一般の方の参加を促します。
■創造・学習には、住民、行政、大学が連携します。
自然の創造や来訪者への説明・手助けは、行政(国・県・村)と地元、さらに大学(教官・学生)が連携して進めます。
鷲巣(わしず)谷第1砂防ダム
この砂防ダムは、大雨の時、鷲巣谷から流れ出す土砂を減らし、根尾川や揖斐川の安全を増すために設けられました。ダムは、地元が進めている淡墨公園構想の拠点の一つとして位置づけられ、管理用と散策路を兼ねた通路をダム直下に設けて、流れ落ちる水を裏から眺めることができる構造となっています。これは、日本で初めてのものです。また、周辺の景観との調和を図るため、表面を石張り(御影石)にするとともに、曲線を取り入れた柔らかい形を演出しました。
ダムの高さは11m、長さは43mで、平成6年に本体に着手し、平成8年3月に完成しました。
下辻谷第2砂防ダム
平成元年9月の集中豪雨により、久瀬村の小津川支川下辻谷では大きな災害が発生しました。下辻谷第2砂防ダムは、再び土砂が流出しないようにと計画されましたが、ダムは東海自然歩道に隣接しているため、巨石を前面に積んだ後ろにコンクリートを打つ工法を採用しました。ダム天端から流れ落ちる水が、巨石に当たることにより複雑な流れを作り、自然な景観を演出しています。また、巨石にもいろいろな表情があり、味わいが出ていると思いませんか?
ナンノ谷床固工群
越美山地にある3大崩壊のひとつである、ナンノ谷大崩壊は明治28年に発生したもので、崩れ落ちた土砂の量は1,530,000立方メートルに及びました。この崩れによって川がせき止められ、天然のダムができました。天然ダムは、その後決壊し土砂を伴った洪水は下流に大被害を与えました。それから、砂防ダムなどが整備されましたが、上流側の川底や川岸を崩れないよう固め、土砂が流れるのを防ぐ「床固工」「護岸工」を、昭和61年から行っています。この床固工群のある地区は、坂内村が行つているバイクレースの開催地でもあるため、地域を応援する意味でも、整備にあたってさまざまな工夫をしました。
昭和61年から、川上地区では毎年オフロードバイクの耐久レース、エンデューロ大会が開催されており、地域活性に大きな役割を果しています。そのため、床固工群の工事に当たっては、地元の方々と話し合いを行いました。そして坂内バイクランドの整備と関連づけ、護岸工事の傾斜をゆるくして観客席を兼ねた階段式にしたり、自然石をはったりして、景観への配慮と、地域への支援を兼ね備えたものとしました。また、周辺にはさまざまな樹木の植栽を流域の人々と行なっており、自然と一体となった整備を目指しています。
| 【環境に配慮した砂防施設(その1)-地域活性化の核となる砂防事業の推進】 |
 |
 |
▲ナンノ谷床固工群
〔大ダワ公園整備事業〕(坂内村) |
▲鷲巣谷第1砂防ダム
〔淡墨公園整備事業〕(根尾村) |
| 【環境に配慮した砂防施設(その2)-自然景観に配慮した施設】 |
 |
 |
 |
| ▲下辻谷第2砂防ダム(久瀬村) |
▲寺谷第1砂防ダム(藤橋村) |
▲井口第3砂防ダム(坂内村) |
| 【環境に配慮した砂防施設(その3)-魚にやさしい魚道】 |
 |
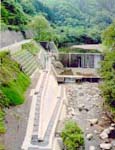 |
 |
 |
| ▲坂内砂防ダム魚道(坂内村) |
▲川上砂防ダム魚道
(坂内村) |
▲根尾西谷川砂防ダム魚道(根尾村) |
▲河内砂防ダム魚道(根尾村) |
HOME