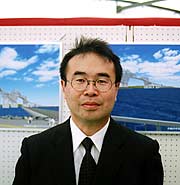建設グラフインターネットダイジェスト
〈建設グラフ2005年10月号〉
interview
■東京ゲートブリッジ
我が国の首都拠点港湾・東京港に新たなランドマーク
国際都市・東京の経済再生に向けて力強い槌音
国土交通省 関東地方整備局 東京港湾事務所 水谷 誠 氏
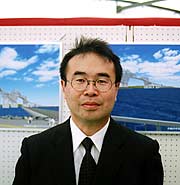 |
水谷 誠 みずたに・まこと
| 昭和 |
36年 |
10月 |
12日生 |
| 愛知県名古屋市出身 |
| 昭和 |
60年 |
3月 |
東京大学工学部土木工学科卒業 |
| 昭和 |
62年 |
3月 |
東京大学大学院工学系研究科土木工学専門課程修士課程修了 |
| 昭和 |
62年 |
4月 |
運輸省入省 |
| 平成 |
4年 |
8月 |
運輸省第三港湾建設局神戸調査設計事務所技術開発課長 |
| 平成 |
7年 |
8月 |
運輸省第二港湾建設局企画課補佐官 |
| 平成 |
9年 |
7月 |
運輸省港湾局計画課補佐官 |
| 平成 |
11年 |
7月 |
運輸省第三港湾建設局高知港湾空港工事事務所長 |
| 平成 |
12年 |
6月 |
アジア開発銀行 |
| 平成 |
15年 |
7月 |
国土交通省国土交通政策研究所研究調整官 |
| 平成 |
16年 |
4月 |
国土交通省関東地方整備局東京港湾事務所長 |
|
8月18日に、東京港の中央防波堤で、東京港臨海道路ⅱ期事業の着工式が行われた。その中心となる東京港臨海大橋は、現代における最先端の土木技術を駆使して1,400億円を投じて行われる世紀の大事業だけに、当日は炎天下の中、200人もの関係者が集まり、多数の報道関係者が詰めかけた。この臨海道路が完成すると、大田区城南島から江東区若洲へダイレクトに通行でき、物流の大幅なスピードアップが可能となることから、それによる恩恵は年間300億円と期待される。その波及効果の広さから、結節点となる大田区、江東区だけでなく、中央区、品川区、港区各区長ら、周辺区の関係者も着工式に出席し、橋脚基礎工の1番杭の打ち込みを祝福した。この大事業を前線で指揮する関東地方整備局東京港湾事務所の水谷誠所長に、事業の概要と施工内容などについて、語ってもらった。

- ――東京港の近況について伺いたい
水谷
-
東京港は、世界の基幹航路のコンテナ船が多数寄港するメインポートとして、また国内海上輸送の拠点港湾として、首都圈4千万人の生活と産業活動を支える重要な役割を果たしています。日本全体の約1/4のコンテナを取り扱う我が国最大の国際貿易港ですが、近年は特に輸入貨物の増大に伴って、外貿コンテナ貨物の取扱量が大幅に伸張しており、平成15年には300万teuを突破し、現在7年連続して日本一となっています。
現在の東京港のコンテナターミナルは、大井と青海の両ターミナルが主力で、このうち大井ターミナルについては、高規格化のための再編整備がh15年度に終了し、-15mの大型岸壁を7バースも有する日本屈指のコンテナターミナルとなっています。
- ――いよいよ東京港臨海道路が着工になりましたが、事業計画の概要についてお聞きしたい
水谷
-
この東京港臨海道路は、東京港のコンテナターミナル相互及びコンテナターミナルと後背地とを結ぶために、大田区城南島から中央防波堤外側埋立地を経由し、江東区若洲にいたる総延長8kmの臨港道路です。この道路は、将来の物流基地としての展開が期待されている中央防波堤地区からのコンテナ貨物などを円滑にさばくため、昭和63年に港湾計画に位置づけられました。
このうち、城南島から中央防波堤外側埋立地にいたる3.4kmは、東京都が平成5年度から沈埋トンネル方式で整備を行い、平成14年4月11日に供用を開始しています。このi期事業に続く、中央防波堤外側埋立地から第3航路を横断し、江東区若洲に至る約4.6kmの区間がⅡ期事業です。
- ――これが完成したときのメリットは、かなりのものが期待できそうですね
水谷
-
このⅡ期事業の完成により、中央防波堤外側埋立地と新木場が12分で結ばれ、港湾の背後地への貨物の円滑な輸送や、既設の湾岸道路の混雑緩和に大きく貢献することになります。その経済効果は、年間300億円程度と試算されています。
- ――Ⅱ期事業は、トンネル形式とはならなかったのですね
水谷
-
2期事業の道路延長のうち、約3/4は、橋梁で構成されています。Ⅱ期事業のうち、第3航路を跨ぐ約2.6kmの区間は橋梁構造によって整備します。その理由は、Ⅱ期事業の区間が、Ⅰ期事業の区間に比べて羽田空港の制限表面による高さ制限が若干緩和されていることと、一般廃棄物の処分場に建設されるため、「廃棄物の処理と清掃に関する法律(廃掃法)」の規定から、トンネル構造とすることが困難だったためです。
- ――構造的な特徴は
水谷
-
建設地の環境・条件において橋梁構造とする上では、高さ制限があるために、部材を三角形に組み合わせたいわゆるトラス形式を採用し、デザイン上の配慮から中央部に開放感のあるトラスボツクス複合構造としています。全長は2,933mに及び、計画交通量は1日35,400台を見込んでいます。
車線は往復4車線を基本としていますが、一部は6車線となります。車道の他に歩道も設けられるので、歩行者も通行できます。東京港臨海大橋の歩道から、海抜60mの壮観な景色を眺望することができます。
 |
| ▲すべり型免震支承 |
 |
| ▲縞鋼管継手 |
- ――かなり大規模なスケールの橋梁ですが、施工上の課題は
水谷
-
臨海大橋は第3航路を横断する橋梁であるため、幅310m以上の主径間が必要になります。また、羽田空港に発着する飛行機や、第3航路を航行する船舶の障害とならないよう、高さは98.1m以下、桁下が54.6m以上という空間の制約があります。こうした条件を総合的に判断した結果、トラス構造を採用したわけです。
さらに、さまざまな先進的な技術を導入して、コスト縮減に取り組んでいます。たとえば、トラス構造に高強度の鋼材を用いることによって、鋼重量を削減しています。また、支承部においては、すべり型免震支承を用いることにより、支承の小型化を図っています。
その他、橋脚基礎の鋼管抗(こうかんぐい)の継手には、せん断抵抗の高い縞鋼管継ぎ手を採用することにより、鋼管の本数を大幅に削減しています。
- ――どんな手順で施工されますか
水谷
-
施工工程は、臨海大橋の橋脚のうち、9本は海上に設置します。このため、橋脚を設置する場所まで建設機械や資材を搬入するための仮設の桟橋や、橋脚を建設するための仮設の桟台を設置します。次に橋脚を支える地下構造物を築造します。
そして、本体は長さ80mの鋼管杭を海底に打ち込んで井筒状に壁を形成し、その内部にコンクリートを打設して基礎とします。
次に、基礎の上部に鉄筋コンクリート製の橋脚を築造します。主橋脚は5階建てのビルに相当する大型の構造物であるため、鉄筋の組立、コンクリートの打ち込みを数メートルずつ繰り返して橋脚を製作していきます。
最後に、橋桁を橋脚にのせ、舗装などの仕上げを行って、橋梁は完成します。
現在、主橋脚を築造する現場では、仮設桟橋、仮設桟台が概成しており、そして8月の着工式をもって、いよいよ橋脚基礎の1番杭を打ち込む運びとなりました。
- ――この事業の施工を通じて、新技術の開発も期待できますか
水谷
-
事業実施に当たっては、私たちは技術検討委員会等の委員会を組織し、最先端の技術を用いて、経済的でかつ機能性が高く、景観にもすぐれた橋梁を整備すべく取り組んでいますが、特にその設計と上部工、下部工に関する技術検討は、関東地方整備局横浜港湾空港技術調査事務所が担当しており、新たな技術開発に当たっています。
 |
| ▲トラス格点構造(従来構造と今回の構造) |
- ――成果は得られましたか
水谷
-
建設地の環境・条件において橋梁構造とする上では、高さ制限があるために、部材を三角形に組み合わせたいわゆるトラス形式を採用し、デザイン上の配慮から中央部に開放感のあるトラスボツクス複合構造としています。全長は2,933mに及び、計画交通量は1日35,400台を見込んでいます。
車線は往復4車線を基本としていますが、一部は6車線となります。車道の他に歩道も設けられるので、歩行者も通行できます。東京港臨海大橋の歩道から、海抜60mの壮観な景色を眺望することができます。
- ――羽田沖の土壌は脆弱で、空港の沖合展開では当時の施工担当者もかなり技術的に悩まされたとのことですが、橋脚基礎の強度に懸念はありませんか
水谷
-
橋脚基礎工に用いる大口径鋼管杭については、載荷試験を実施しました。杭先端の閉塞率を含めた支持力機構を明らかにするため、平成15年度に現地で試験杭を打設し、押込や水平などの静的載荷試験や、急連載荷試験と衝撃載荷試験を実施したわけです。
その結果、地盤性状の厳密な把握ができ、橋脚の基礎構造を小さくすることが可能となりました。なお、本試験で打設した鋼管杭は、橋脚施工のために建設する仮設桟橋の一部として有効に活用しました。
 |
 |
| ▲着工式には関係者が多数出席した |
|
- ――建設資材については
水谷
-
BHS鋼材を使用しています。何しろ、東京港臨海大橋は大規模なトラス構造の橋梁であるため、橋梁用高性能鋼材(BHS鋼材)を導入し、橋梁上部工の重量軽減を図ることが必要です。このBHS鋼材は、通常の鋼材と比較して高い強度を有しており、溶接などの施工性を確認するため、平成16年度に組立試験などを実施しました。
こうした橋梁用高性能鋼材は、米国では既に使用された事例もあるのですが、わが国ではこれまでに事例が無く、初めてのケースとなります。
この他に、トラス格点構造などの構造形式の工夫もしています。トラス構造としては、国内最大級のトラス橋梁となり、部材も大きくなるので、格点部をトラス弦材と一体構造とし、コンパクト化する設計を行っています。
また、近年の車両の大型化などによる床版への荷重が鋼床版の疲労として、どこの橋梁でも顕在化しているため、鋼床版の詳細構造については、鋼床版を構成する部材の形状や板厚の工夫により応力の集中を避けることで、疲労破壊を防ぐデザインの検討を行っており、昨年度よりfem解析や実物大の模型実験による検証を実施中です。
 |
| ▲現場の施工状況 |
- ――今後の事業の進捗状況と今後のスケジュールは
水谷
-
設計は平成15年度までで基本設計と主橋脚および端橋脚の詳細設計を終了しており、16年度はその他のアプローチ部の詳細設計を実施しました。メイン上部工の詳細設計は17年度にかけて実施しています。
現地での工事は、昨年度は橋脚建設のための仮設桟橋築造工事を実施しており、海上部橋脚の相当部分の工事発注を行いました。
上部工は18年度以降の着手となります。なお、この建設事業は国の直轄事業ですが、陸上部分の施工については、廃棄物地盤であるため種々の手続きが必要であり、東京都に委託しています。
今後とも私たちは、工事安全の確保に留意し、一日も早く臨海道路ⅱ期事業の供用ができるよう、全力をあげて取り組む所存ですので、関係各位のご理解、ご支援をお願いしたいと思います。
- ――関係者への事業の周知や、一般者への広報はどのように行っていますか
水谷
-
事務所としてホームページを開設し、公開するだけでなく、「tokyo portal sight」という地域広報誌を発刊し、単なる工事情報だけでなく地域に関する幅広い情報提供を行っています。
多くの方々に関心を持って頂き、それらの媒体を通じて、事業を知ってもらいたいと思います。
首都圏の未来を拓く・東京港臨海道路Ⅱ期事業
HOME