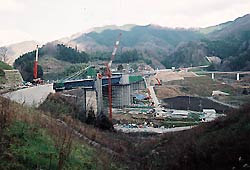建設グラフインターネットダイジェスト
〈建設グラフ2005年2月号〉
interview
47年豪雨で2万8,000戸が浸水
志津見ダムと尾原ダムで将来不安を解消
国土交通省 中国地方整備局 斐伊川・神戸川総合開発工事事務所長 則松 秀晴 氏
 |
則松 秀晴 のりまつ・ひではる
| 昭和 |
56年 |
3月 |
九州大学大学院工学研究科 修了 |
| 昭和 |
56年 |
4月 |
水資源開発公団(現:水資源機構)入社 |
| 昭和 |
56年 |
4月 |
水資源開発公団試験所第二試験課水理試験室に配属 |
| 昭和 |
59年 |
4年 |
水資源開発公団阿木川ダム建設所ダム工事課 |
| 昭和 |
61年 |
4月 |
水資源開発公団川上ダム調査所調査設計課係長 |
| 平成 |
元年 |
4月 |
水資源開発公団味噌川ダム建設所ダム工事課工事第3係長 |
| 平成 |
3年 |
4月 |
建設省土木研究所ダム部ダム構造研究室主任研究員 |
| 平成 |
6年 |
4月 |
水資源開発公団日吉ダム建設所調査設計課長 |
| 平成 |
8年 |
4月 |
財団法人水資源協会調査部次長 |
| 平成 |
9年 |
7月 |
水資源開発公団中部支社建設部技術参事役(徳山ダム建設所勤務) |
| 平成 |
10年 |
4月 |
水資源開発公団徳山ダム建設所副所長 |
| 平成 |
12年 |
4月 |
水資源開発公団本社技術管理・工事検査室審議役 |
| 平成 |
13年 |
1月 |
水資源開発公団本社技術管理・工事検査室調査役 |
| 平成 |
14年 |
10月 |
水資源開発公団小石原川ダム調査所長 |
| 平成 |
16年 |
4月 |
国土交通省中国地方整備局斐伊川・神戸川総合開発事務所長 |
|
斐伊川・神戸川流域は、低地帯であるために河川の疎通能力が低く、しかも河川水面が高くなっているので、溢水時の被害の大きさは計り知れない。そのため、明治年間から治水計画が検討されてきたが、それに伴う住居移転などの代償も大きいために、日の目を見ることなく長い年月が経過した。そして昭和47年には、ついに水害で市街地が川となり、2万8,000戸が浸水するという惨状を見ることになった。それを契機に、上流部で志津見ダム、尾原ダムなどを含む総合治水対策が加速的に構築され、100年の構想が結実した。これらのダム建設に当たる斐伊川・神戸川総合開発工事事務所の則松秀晴所長に、地域事情と事業計画などを伺った。
- ――斐伊川・神戸川の総合開発事業からお聞かせ下さい
則松
-
現在、神戸川、斐伊川の上流でそれぞれ志津見ダム、尾原ダムを建設していますが、これは壮大な斐伊川・神戸川治水計画の中の一部です。松江市と接したところに宍道湖と中海という湖がありますが、日本海とはそれほど高低差がなく、洪水が起きた場合は斐伊川の水が流れ込み宍道湖の水位が急速に上昇するのです。その上に、宍道湖と中海を繋ぐ大橋川の疎水能力が非常に低いため、河川水が流入したときに大橋川から水が抜けられないので、水位はさらに上がる一方となり、地域全体が浸水するのです。
島根半島にはさまれたこの地域は、かつては海で徐々に砂が堆積して陸地になったということです。そのため、全体的に土地としては低く、宍道湖の水位が上がれば水没してしまうおそれがあります。このように、宍道湖の水位を低下させることが治水上の大きな課題となっています。
そこで、まずは大橋川の疎通能力が問題で、加えて中海と宍道湖の高低差が少ないので、現在の流路を拡大しなければなりません。ところが大橋川周辺は松江市の中心部にあり、そのためには移転者がかなりの数に上ります。計画としては、古くは江戸時代に松江藩が立案したこともあるようですが、やはり移転者数があまりにも多いために現実的ではないとの結論に至ったのです。
そこで、宍道湖に流入する流量自体を減らす発想となったわけです。一つは分流です。宍道湖に流入する斐伊川の水をバイパスし、神戸川へ流すのです。その方法ならば大橋川の改修も小規模で済みます。
もう一つは上流部でのダム建設です。斐伊川上流に尾原ダムを整備し、洪水のピークをカットします。それによって、洪水の最大流量を減らしてバイパスに通す水量を減らすことができます。
また、神戸川の馬木から下流の区間では、斐伊川から新たに水が流れ込むことになります。今までの流量に新たに加わるわけですから、あまりに水量が多いと下流区間で大変な流量になってしまいます。そのため、大規模な川の拡幅が必要となり、たくさんの家屋に移転してもらわなければならなくなるので、やはり神戸川上流の段階で絶対的な水量を減らす必要があるのです。流量の多くなる下流域はそれでも拡幅する必要がありますが、まずは神戸川上流のダムで、ある程度ピークをカットすることが必要で、そのために現在建設されているのが志津見ダムです。
かくして、全体的に水量を減らし、一部を神戸川に流して宍道湖の水位の上昇を防ぐという計画で、上流のダム群、中流の斐伊川放水路と斐伊川の改修、そして下流での大橋川改修と宍道湖湖岸堤整備の3点セットが、総合治水対策の全容です。その中の斐伊川上流の尾原ダム、神戸川上流の志津見ダムを当事務所が担当しています。
これらは、古くから大変な苦労を負ってきた地域の長い歴史の中で構築された100年の体系というべき計画なのです。
- ――この計画が正式決定した直接のきっかけは
則松
-
昭和47年7月の豪雨がひとつの契機となりました。宍道湖の水位の上昇によって、斐伊川流域では浸水戸数が28,219戸にも上り、浸水農地も10,031m2に上りました。特に典型的なのが出雲空港で、10日間も水没し、完全閉鎖されてしまいました。さらに夜間閉鎖は約210日にも及びました。

- ――この地域は、全国的にも珍しい地形なのでしょうか
則松
-
そうです。斐伊川上流域の大部分は、良質の砂鉄を多く含む風化花崗岩に覆われており、古くから砂鉄を原料とした「たたら製鉄」が行われてきました。風化花崗岩を崩して川に流すと、砂鉄だけが比重が重いので土砂が流れて沈みます。その砂鉄を集めるわけです。「鉄穴流し」という採取方法です。砂鉄を採取した後の大量の土砂は河川に流されたため、「たたら製鉄」が盛んになるにつれて斐伊川の川床に溜まって行きました。その経緯から川の底が高く、周りが低い天井川となり、洪水時に川から水が溢れると戻ることがなく溢れ続けてしまう状況です。
 |
| ▲松江駅前通り |
 |
| ▲大正町通り |
- ――そうした地形から、47年の水害では街の中がほとんど浸水してしまったのですね
則松
-
街が川になってしまう状況で、しかもなかなか水が引かないわけです。何しろ斐伊川から水が補給され、中海と宍道湖を繋ぐ大橋川に流量能力がないので、宍道湖からの溢水には際限がありません。この47年の水害から約30年が経過していますが、それを経験した世代の人々は今でも危険だと主張します。
この30年間は幸いにも大災害は起きていないので、記憶も風化しつつありますが、昨年の新潟豪雨のような降雨が、いつ起きても不思議ではないのです。梅雨前線がわずかでも南に停滞したら、この地域でも同様の雨が降り、しかも雨水に弱いので、47年の豪雨がいつ再現されてもおかしくはありません。この30年間は、幸いにもそれが避けられているだけのことですから、急がなければならないというのが我々の認識です。
- ――志津見ダムの機能は、洪水調節に限定されているのでしょうか
則松
-
メインはやはり洪水調節です。有効貯水容量が4,660万m3ですが、そのうちの4,000万m3は洪水調節容量で8割を占めています。そのほか640万m3ほどの利水容量もありますが、それは河川環境の保全に利用します。川の水枯れを防ぐためには、常に一定の水を川に流して環境を保全します。
この他の利水は、工業用水70万m3と発電140万m3で、洪水容量に比べると小規模です。したがって、容量的には洪水調整と河川環境保全に重点を置いたダムと言えます。
 |
| ▲国道184号開通式 |
- ――昨年度からようやく着工しましたね
則松
-
今年3月にダム本体工事を発注し、ダムの基礎掘削を行っていましたが、11月27日に付替国道184号の全線供用を開始したことで、河床沿いに通っていた現道が切り替えられ、全面的な基礎掘削の展開が可能になりました。
- ――観光資源が豊富な地域なので、地域住民のみならず観光客にとっても利用しやすくなりますね
則松
-
従来の道路は幅員が4m程度しかない狭い道で、行き違いも大変だったのですが、片側一車線ずつの道路が完成し、なおかつ時間的にもかなり短縮されたことで、快適で安全な通行ができるようになりました。
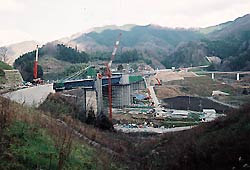
- ――ダムの観光資源としての活用などは検討されていますか
則松
-
地元では国道と県道が交差するエリアを観光資源に活用したいとの希望があります。志津見ダムは、専門用語では「穴あき坊主」と呼ばれるタイプのダムで、常に洪水量を空けておくため、常時の水位は低い位置にあります。そのため広い土地が空いています。そこで、現在でも「東三瓶フラワーバレー事業」として、春にはポピー祭り、秋にはコスモス祭として地元特産品の展示・販売、写真撮影会などが毎年行われています。平常時に水に浸かることのない場所を利用してイベントに活用するというのは、ダム開放施策としても有効だと思います。
事務所としても、斐伊川・神戸川治水事業のパネル展示や、現場見学会などを実施していますが、将来的にもこれらの取り組みを継続していくと同時に、広い敷地をさらに有効活用しようと考えています。
- ――志津見ダムの工事進捗状況は
則松
-
現在は基礎掘削を進めていますが、18年度にはコンクリート打設を開始し、20年度にコンクリートを打ち終え、その後試験湛水という工程になります。
完成は尾原ダムと同時期(22年度)を予定していますが、志津見ダムは尾原ダムより少し先行しており、湛水が順調ならば、余裕をもって完成となるでしょう。尾原ダムも何とか志津見ダムに追いつこうというかたちで頑張っています。
 |
| ▲FBC工法 |
- ――ダムの施工においては、新技術などは採用していますか
則松
-
尾原ダムで軽量盛土工法のFCB工法を採用しています。これはセメント、水で構成される通常のセメントミルクに気泡を混入させた「気泡混合セメントミルク」を盛土材として用いた工法です。土やコンクリートに比べて軽く、流動性があり、さらに硬化後は自立するために直立の盛土が可能で構造物への土圧が軽減できます。また、施工前の体積は運搬材料の約2分の1なので、運搬コストが削減できます。
志津見ダムでは、従来には見られない複合トラス形式を志津見大橋で採用しています。これはフランスを中心としたヨーロッパで開発された構造で、従来のpc箱桁の自重30%を占めるコンクリートウェブを鋼トラスに置き換えた橋梁です。
特に、景観面から桁下地形の変化に対応してトラスの桁高を変化させており、このような複合トラス橋は国内では初めての施工例となります。さらにpc橋脚位置は複合トラスとコンクリート箱桁の連続構造となっているのですが、これなどは世界でも初の施工例です。従来は、コンクリートだけか、または金物だけで構築された橋が多いのですが、コンクリートと金物を合体した珍しい事例です。
 |
 |
| ▲再生植生マルチング材使用状況 |
▲伐木材の粉砕状況 |
- ――コスト縮減に向けては、どのような工夫が行われていますか
則松
-
ダム堤頂部の形状を、従来とは異なるスリムなかたちにしています。ダムの堤頂部は、通常は橋梁のように繋がって、通れるようにするのですが、このダムの場合は堤頂部を通って対岸で道路とは繋がっておらず、車両交通としては行き止まりの扱いとなります。そのため橋をカットし、水が越流している部分を歩く仕組みとしました。これで5億円の縮減になります。
また、掘削跡を緑化するために伐採した木を、チップ化して植生工に再利用しています。これは尾原ダム、志津見ダムともに共通の取り組みです。
 |
▲小学生による植樹
(平成15年・尾原ダム) |
 |
| ▲どんぐり引き渡し式 |
- ――環境への配慮については
則松
-
「1000年の森づくり」、「どんぐりの森づくり」という活動に取り組んでいます。例えば、地元の小学生にどんぐりを拾ってきてもらい、下流の松江市内の小学生に苗つくりのための竹ポットを作ってきてもらう。それを持ち寄って一緒に苗を作り、それを育てて山に植えるのです。尾原ダムを中心に、そうした活動の輪を広げています。
そして、子供たちが大人になったときに見に来てください、とよく話しています。このどんぐりの森づくりでは、竹ポット・どんぐり引き渡し式、植樹祭といったイベントを実施していますが、npo法人のご協力もあり年々参加校・人員とも増えています。また、何よりも上流・下流の小学生の交流の場として、非常に意味のある活動となっています。
また、フラワーバレーの周辺を「彩りの森」にしようと地元の頓原町が活動を始めており、秋に紅葉を楽しめるように、イベントがある度に参加者に植樹してもらう活動をしています。
- ――「彩りの森」は、四季を通じて彩りが見られるものになるのでしょうか
則松
-
今のところはもみじを植えています。桜はどこでも見られるので、差別化を図っているわけですね。当面は、紅葉シーズンに焦点を当てて色とりどりの赤を見せたいと考え、町が主体となって活動をしています。何しろ、日常では見られない水面があり、せせらぎもあります。これから整備された道路ができて、上手く使っていただければ、有力な観光資源になると期待しています。

- ――誰もが今まで顧みなかったところが、観光資源としての価値を得て注目を集めるようになりますね
則松
-
そうです。我々は基盤整備を中心に実施しており、あくまで主体は地元です。したがって、町から様々な希望を出してもらえれば、それをインフラでサポートするという中で協力関係も生まれてきます。まずは、地元の方々に愛されるダムであるということが何よりも重要であると考えています。
- ――情報公開や広報活動は、どのように行っていますか
則松
-
情報発信基地としての尾原ダムPR館が、尾原ダムの工事分室の付近にあります。また、事務所のホームページでも、工事の進捗状況やイベント情報などを閲覧できるようにしています。
志津見ダム安全協議会
HOME